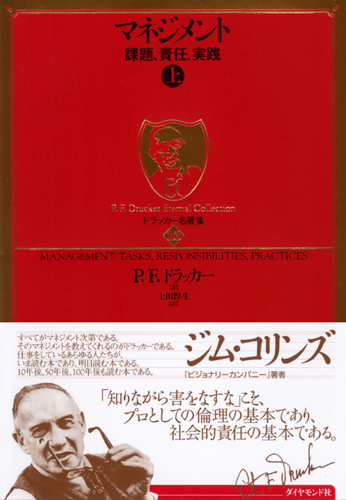ドラッカーの書籍によく登場するフレーズに、
「誰が正しいか」ではなく「何が正しいか」が大事である
というものがあります。前者は人に着目し、後者は事実に着目します。
「人間は社会的動物である」とはアリストテレスの言葉ですが、人間は一人では生きられず、他人との関係や絆というものはなくてはならないものです。
そうであるがゆえに、人には好き嫌いが生じ、敵味方という峻別をつくりやすく、好きな人や味方が言うことはすべて正しく、嫌いな人や敵が言うことはすべて間違っている、という思考に陥りがちです。
敵の言うことに賛意を示そうものなら、「お前はどっちの味方なんだ」と言われ、仲間内で非難を受けることにもなりかねません。
人間がそのような思考になりがちであることは認めざるを得ませんが、組織においてそれを野放しにしていては、組織がよくなることはなく、目標の達成もままなりません。
だからこそ、意識して「誰が正しいか」ではなく「何が正しいか」が大事であることを受け入れ、日頃から明言し、行動に表していかなければなりません。組織の姿勢として習慣化し、文化として築いていかなければなりません。
「罪を憎んで、人を憎まず」も大切な言葉です。「誰が間違っているか」と犯人探しに躍起になるのではなく、「何が間違っているか」に意識を向けます。
「誰もが同じ間違いをする可能性がある」ことを認めたうえで、「どうしたら改善できるか」を皆で考えていくことが、健全な組織運営と言えるのではないでしょうか。
「何が正しいか」より「誰が正しいか」を重視することの弊害
妥協から入ってしまう
何らかの課題に対処するため、会議の場で意見を出し合い、意思決定をする場面を想定してみましょう。
5名の参加者がいたとして、それぞれ意見を述べていきます。
そこで「誰が正しいか」を気にするとどうなるでしょうか。「5名の意見の中からどれを選ぶか」という発想になることが普通です。
参加者の中に、仲の良い人や悪い人が混ざっていたら、仲の良い人の意見に賛同したくなるでしょう。仲の悪い人の意見に賛同しようものなら、後から裏切り者扱いされるかもしれません。
結局、「誰が正しいか」を重視するということは、それぞれの意見の中から選択するということであり、最初から妥協しているのと同じことです。他に良い意見があるかもしれないからです。
一方、「何が正しいか」を重視するとどうなるでしょうか。5つの意見は参考にしつつも、お互いがお互いの意見を聞くことで思考が活性化し、さらに良い案を思いつくかもしれません。
「誰が言っているのか」を離れて、意見そのものに着目するようになれば、どうすればもっと良くなるかを考えて、さらに良いものを加え、練り上げることができるようになるでしょう。
様々な考えやニーズをもったメンバーで構成された組織では、意見の対立は日常的です。意見をまとめようとすれば、必ずといってよいほど妥協がつきものです。
だからこそ、「何が正しいか」をまず重視しなければなりません。ドラッカー曰く、正しいことを知らなければ、正しい妥協さえできないからです。
思考停止に陥る
「誰が正しいか」という発想は、「味方の言うことは正しく、敵の言うことは間違い」という発想に陥るのと同様、「その人が言うことだから正しい、その人がすることだから正しい」という発想に容易に陥ります。
特に成功した経営者であれば、部下は容易にそのようになってしまうでしょう。経営者の言うとおりにしておけばよいということになれば、部下は思考停止に陥ります。
経営者でなくとも、組織内で派閥のようなものが生じていれば、「どちらにつくか」ということが問題になり、「何が正しいか」という発想は失われてしまいます。政治的な離合集散、与党を追い落とすためだけの野党連合のようになります。
そのような状況には、経営者の姿勢が反映されていることは間違いありません。「何が正しいか」ではなく「誰が正しいか」を重視してきた経営者の姿勢の影にしかすぎません。
ドラッカーの著書である『企業とは何か』に同種の例が出ています。本書は、ドラッカーがGMを調査してまとめた書籍です。『現代の経営』の前身に当たる書籍で、大きな反響を得たものです。
当時の名経営者であったスローンは、事業部制など様々な仕組みを導入し、すぐれたマーケティングを行って、フォードを追い落としました。
ドラッカーは、GMを隈なく調査したうえで、GMの優れた点を経営の体系として普遍化し、一方で、GMがより素晴らしくなるために、今後起こるであろう問題を指摘し、すぐれた提案もしました。
ところが、GMは本書を完全に無視し、同社内では事実上なきものにしたと言います。
GMの認識としては、自分たちは物理の法則のような絶対的な原理を発見したと考えており、間違いなどないということでした。
しかし、ドラッカーの考えは、経営政策というものは人が考えたものであるから唯一絶対たりえず、せいぜい、正しい問いを見つけるための問題提起にすぎないということでした。まさに、「誰が正しいか」ではなく「何が正しいか」が重要であるということです。
なお、スローンの後継候補であったウィルソン(後のアイゼンハワー政権下での国防長官)は、本書に賛同し、社内に取り入れようとしましたが、スローンをはじめとする経営陣や労働組合の反対を受けて、断念せざるを得なかったと言います。
スローンは、「常に正しいのは顧客である」と考え、優れたマーケティングによって大きな成功を得たと思いますが、その成功によって「常に正しいのは私である」になってしまったのかもしれません。
失敗や問題が無視される
「誰が正しいか」に関心をもつ人は、「誰が間違っているか」や「失敗したのは誰か」に関心をもつことにもなります。間違いや失敗が起こったとき、それらに対処する前に、「誰の責任か」という犯人捜しを重視します。
そういう人を上司にもつ部下たちは、間違いや失敗を明らかにし、正そうとするのではなく、間違いや失敗を隠そうとするようになります。
問題が起こっていることに気づいても、「報告すると自分の責任にされるかもしれない」、「自分が後始末をさせられるかもしれない」と考えるようになり、見て見ぬふりをするようになってしまうでしょう。
犯人捜しをする本人はどうでしょうか。おそらく、自分が間違ったとしても、決して自分の間違いを認めようとはしなくなるでしょう。
組織にとって、失敗や問題が隠蔽されることほど致命的なことはありません。隠蔽できないほど明確になったときには、もはや手遅れになることでしょう。
「何が正しいか」に集中する方法
人には好き嫌いがあり、感情に左右されやすいからこそ、意識的に「誰が正しいか」ではなく「何が正しいか」に焦点を合わせる取り組みが必要になります。
「誰が正しいか」ではなく「何が正しいか」が大事であることを価値基準とする
まずは、「誰が正しいか」ではなく「何が正しいか」が大事であることを価値基準とする旨を表明しなければなりません。
さらに、実際に価値基準として確立すべく、経営者自らが日常的に実践しなければなりません。
会議の場では、意見の対立が起こるたびに、何度でもその旨の表明し、意見を出した人ではなく意見そのものに参加者の意識を集中させなければなりません。
経営者自身の意見に対しても、積極的に問題指摘や反対意見、改善意見を出させ、それらを前向きに評価する姿勢を示さなければなりません。
QC活動などでは、「何が正しいか」に集中するため、参加者が車座などのように向かい合うのではなく、学校方式のようにホワイトボードなどに向かいます。
意見はすべて書き出すことで見える化しますが、意見を出した人ではなく書き出された意見(ホワイトボードなど)に向かうことによって、人と意見を意識的に切り離し、より良い考えや提案は何かを考えることに集中します。
通常の会議でも、意見は書き出し、意見そのものに意識を集中させようとすることは効果的です。
さらに、経営者は、自身の意思決定が間違っていたことに気づいたなら、速やかに認め、改善を提案し、実行しなければなりません。
意思決定に間違いや失敗はつきものであること、間違いや失敗がいけないのではなく、間違いや失敗から学び、改善していくことが組織を前進させるための知恵を与えてくれることを身をもって示さなければなりません。
誰もが正しいことを前提とする
「何が正しいか」に集中しようとする場合でも、意見が対立すると、2つの意見を比較して、「どちらの意見が正しいか」という発想になりがちです。結局、二者択一の思考になってしまいます。
このような思考を避ける方法として、ドラッカーは、「誰もが正しい」という前提をもつことを提案しています。
ドラッカーあるいはドラッカーの考えのもとになったメアリー・パーカー・フォレットによると、意見の相違の多くは「何に対する意見か」についての認識の違いから生じると言います。
つまり、「どれが正しく、どれが間違っている」ということではなく、それぞれ「違った現実を見ている」ということであり、それぞれ「自分が見ている現実に対して正しい意見を述べている」ということです。このことを前提として認めようということです。
本当の問題にたどり着く
「誰もが正しい」ことを前提とし、「何が正しいか」を考え抜くことによって、本当の問題にたどり着くことができます。本当の問題にたどり着くことができれば、意見の相違というよりは、複数の代替案を手にするのと同じことになります。
「事実に基づいて判断せよ」という言い方をよくしますが、ドラッカーによれば、純粋に客観的な事実というものは存在しないと言います。だから、それぞれ「違った現実を見ている」という状態が生じます。
「群盲象を評す(撫でる)」と言うように、事実を客観的に、ありのままに見るということはできず、「見る」という行為自体がすでに自分独自の基準や価値判断を適用しています。同じものを見ても、人によって違って受け止めるのです。
そのような現実を皆が認識したうえで、まず、違う意見を導き出している認識の違いを明らかにします。
認識の違いは、解消することが目的ではなく、尊重されなければなりません。これが、重要な問題のあらゆる側面を見逃がさないための方法です。
そうやって、本当の問題にたどり着き、その全体像を知ることができるようになります。
(参考:「意思決定」)