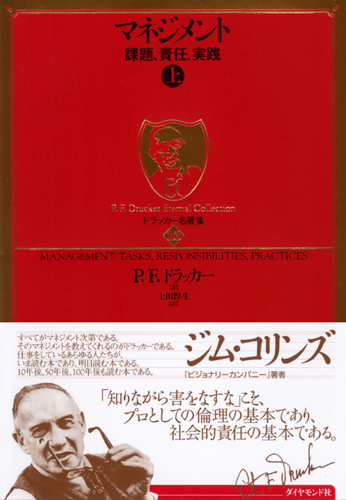18世紀以前には、国王、政治家、あるいは政治思想家で、国家が国民の経済的幸福に責任を負うものであるとか、国民の経済的幸福に関わり合うことができるものであると考える者は、ほとんどいませんでした。
国家の富は、君主の所有する富に関わるものであり、その国に住む一般の人々には関わりがありませんでした。
17世紀、ルイ14世の下で財務総監をはじめ数々の要職についていたコルベールは、道路建設と運河建設に資金を投じる傍ら、フランスの最も貴重な製造業者に対して補助金を与え、免税措置を施しました。さらに海外でのフランス製品が地球の隅々にまで行き渡るように貿易商社を設立しました。さらに、海外でのフランス製品に対する購買意欲を高めるために、品質を保証する数々の手段を講じました。概して、輸出は奨励され、輸入は抑制されました。
ただし、これらはフランス国民の生活水準の向上を図るためではなく、銀を蓄えるために行われました。銀があれば、ルイ14世は戦費を賄え、常備軍を維持できたからです。つまり、君主を富ませるための政策であったのです。
近世絶対主義国家成立期から産業革命開始期まで(16世紀末〜18世紀)の西ヨーロッパ諸国で、資本の本源的蓄積を推進するためにとった経済政策および経済理論は「重商主義」と呼ばれます。
初期産業資本のために国内市場を確保し、貿易を通じて財貨を蓄積することが、国富の増大につながると考えられました。この思想に基づき、国家による輸出促進、輸入制限、植民地の獲得および搾取などが行なわれました。
(出典:コトバンク 日本国語大辞典 )
18世紀ヨーロッパに始まる「愛国主義」
重商主義から大衆的な経済国家主義への転換は、絶対主義から民主主義への政治的転換と軌を同じくしました。民主的な概念や制度が拡がるにつれ、経済および政治の目標は、君主の力を高めることから、国民の幸福へと移行しました。
最初の革命はイギリスで起こりました。市民は相互に道徳的パートナーシップの義務を負っているとされました。この義務を市民に教え込み、それを履行する手段を提供したのが、民主制度でした。
18世紀にイギリスとヨーロッパ大陸において、「愛国心」という言葉が聞かれるようになりました。愛国者とは「自由政府にいる人間で祖国を愛している人、より正確には国民の幸福を願っている人」を指していたといいます。
中欧および東欧の国民は、オーストリアとトルコの政治的支配下にあり、フランスの文化的支配に反抗する気持ちから、自分たち固有の文化に関心を抱いていました。しかし、フランス革命とナポレオン進軍に刺激され、その他の多くの民族も国家のアイデンティティを求めるようになりました。
愛国的な市民は、祖国防衛のときには特に、優秀な兵士であることを証明しました。民主政府も愛国的で教育の行き届いた国民を必要としていました。「良い市民」を生み出すことが合法的な国家の目標となりました。
アダム・スミス以来の議論
愛国心から「国家の市民たる者は経済的な幸福に対して責任を分かち合わねばならない」という概念が生まれました。
18世紀において最も影響を与えた書物の一つにアダム・スミスの『国富論』があります。本書では普遍的な経済原理について述べつつも、その理論は国家的でした。スミスは重商主義を非難しましたが、その理由は市民が貧しくなるからでした。政府が介入したほうが国益に適う場合には、政府が介入することに反対しませんでした。そして、防衛が豊かさよりも重要であると考えました。
国富を基本的に決定する一国の産出高に関して、スミスは2つの基本的な決定要因を明らかにしました。一つは雇用されている人口の比率、もう一つは労働者の一般的な技能、器用さ、判断力です。
アメリカの初代財務長官を務めたアレクサンダー・ハミルトンは、1791年に、国民の富を高める方法として、「製造業者の問題に関する報告」を提案しました。製造業の基盤がしっかりしていれば、国家全体の収入と富が増え、より多くの雇用機会が提供され、その結果、移民が増え、外国資本が引き寄せられ、国家の独立と安全がより確かなものになるだろうと述べました。さらに、「銀行に関する報告」において、国家の通貨供給量を責任をもって管理する中央銀行の設立を提案しました。
ハミルトンは、「アメリカの小規模製造業者は、少なくとも一時的に保護されたり助成されたりしなければ、決して大規模で先進的なヨーロッパの製造業者に追いつくことはできないだろう」と警告し、外国製品への関税とアメリカ製造業に対する補助金を要求しました。ただし、関税は正当な理由が消えても残存し続けるが、補助金は必要がなくなれば取りやめることができるため、補助金のほうを好みました。
自由貿易か保護主義かの論争
関税の是非については、19世紀のアメリカで激しい経済論争の種となりました。関税は共同体の一部に膨大な税金をかけることによってお金を別の人の懐に移し替えるだけだと考える者もいました。
しかし、将来アメリカが経済大国になれるかどうかは関税にかかっていると主張され、関税は国内の改良工事のための潜在的な資金源なるという考えもありました。
1913年以前の輸入品にかけられる平均関税率は50%近くに達し、巨額の金が連邦政府の金庫に流れ込みました。その関税収入の継続的な必要性を正当化するために、一連の国内改良工事への連邦支出を飛躍的に増やしました。
アメリカ人の自己利益の原理
関税は、消費者である国民に割高な買い物をさせるわけですが、当時の論争においては、経済全体に好影響を与え、結果的に関税を払った人々の利益となって返ってくると主張されました。
トックヴィルは「アメリカでは、犠牲はそれによって被害を受けた人々にとって自己利益が啓発されるものとして正当化される」と言いました。アメリカ人は「自分の同胞の役に立つことは自分自身の利益でもあり、また義務でもあるという考えを、あらゆる機会に自分の心に刻み込む」と述べました。関税に関する考え方もこれに相当するでしょう。
19世紀のヨーロッパの人々もまた、国民経済を国民の幸福と結びついたものとみなし始めていましたが、トックヴィルが言うには、ヨーロッパでは、犠牲は愛国心と名誉の見地から正当化されました。人は、それが崇高であるがゆえに、同胞のために犠牲を捧げなければならないとされました。