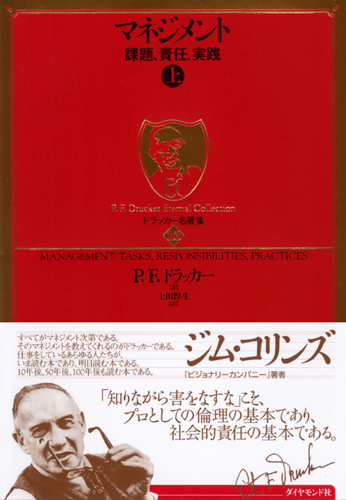世間一般では、アメリカの独立(1776年)がフランス革命(1789年~1795年)と同じ理念に立つとの説がありますが、ドラッカーは、これを歴史の完全な歪曲であると指摘します。
フランス革命は、絶対王政に対する反乱であり、その結果は、全体主義的な恐怖政治でした。その理念は専制をもたらし続け、その後のあらゆる全体主義的哲学の思想と思考に枠組みを与えました。
アメリカの独立は、封建主義の暴政に対する反乱などではなく、理性主義リベラルと啓蒙思想の専制に対する自由のための保守反革命でした。その結果、自由な社会を構築し、その後の西洋の自由にも影響を与えました。
アメリカの保守反革命の理念、原理、制度が、ヨーロッパにおいて負け続けていた反全体主義の保守主義者たちに勝利と力をもたらしました。ヨーロッパには自由な保守主義者が大勢いましたが、アメリカの独立が、彼らの考えを政治行動へと転換させたといいます。何より、自由の基盤としての人間の不完全性への信条を確認しました。
ところが、ヨーロッパのその後の19世紀は、自らの手にした自由が、アメリカの保守反革命の理念によるものであることを忘れ、自由の重大性を忘れたといいます。その結果、自由と自由な社会を手続き上の問題と見る風潮が強まり、19世紀の自由のすべてをフランス革命の功績とすることが常識となっていきました。
ヨーロッパにおけるアメリカ革命対フランス革命
少なくとも1850年までは、ヨーロッパの政治思想において、イギリスが問題解決の道を見つけたということは常識となっていたといいます。
19世紀の自由の基礎が、フランス革命を克服した保守主義にあり、ヨーロッパに関する限り、この保守主義をイギリスが占有していたということも知られていました。
イギリスがフランス革命を克服し、自由な商業社会を発展させることが可能であった理由として、通常、国民性、イギリス海峡、憲法があげられますが、ドラッカーは、いずれも正しくないと言います。
歴史上の展開において、国民性や民族性による説明がなされることは多く、ファシズム全体主義についても、ドイツやイタリアの国民性を理由とするものがありますが、ドラッカーは『「経済人」の終わり』でそれを否定しています。国民性や民族性による説明は、要するに、本当の原因を知らないためにもち出される理由であり、説明できないということを告白しているに過ぎないといいます。
ドラッカーが例示しているように、ナチス・ドイツに対して宥和政策をとったチェンバレンと、戦ったチャーチルのどちらがイギリスの国民性を体しているかは、いずれも同等であるといいます。クロムウェルの全体主義専制と名誉革命のいずれがよりイギリス的であったかも、ドラッカーの答えは「いずれも」です。国民性は、気性や気質であって、理念、行動、意思そのものとは関係ありません。
海峡がイギリスをフランスから守ったことは事実ですが、海峡が自由を生み、自由な商業社会のための制度を生み出したわけではありません。憲法もまた、イギリスに自由をもたらす助けにはなりましたが、憲法自身が自由をもたらすことはできません。
憲法に自由の規定を置きながら、全体主義である国は現に存在します。
現在(2022年)も、コロナ禍に乗じて、自由が失われつつある国もあります。アメリカ、カナダ、フランス、オーストラリア、ニュージーランドなどです。日本もかなりそれに近い状態です。
イギリスに特有の動きとして論じることのできるのは、1688年の名誉革命以降です。当時のヨーロッパでは、30年戦争によって自由な憲法が奪われ、王政に対する中央集権に進んでおり、イギリスでも、クロムウェルの共和政体、王政復古を通じて、全体主義に進んでいるように見えました。そのようなヨーロッパの趨勢から決別したのが、非絶対主義の理念に立つ立憲政治の再建を意味する名誉革命でした。
しかし、その僅か80年後には、イギリスでも立憲制が形骸化し、啓蒙専制主義に陥りかけました。議会は統治機能を失い、下院は王党派に占められ、国王とその官僚が最高権力として支配していました。政治は宮廷の策略とほとんど同義であったといいます。
1776年当時、イギリス政治で脚光を浴びていたのは、功利主義を創設したベンサムでした。ベンサムは、最大幸福原理に基づき幸福計算を提案しました。ドラッカーは、ベンサムを、最も危険なリベラルのファシズム全体主義者であり、世界のために世界を奴隷化すべく無数の計画を練っていたと批判します。
ベンサムは、多数者の利益のために少数者を犠牲にすることを支持しないという意見もありますが、社会全体の幸福を最大化する手法として、快楽の量を計算し、善悪の程度を決定するという考え方は、個人の自由の否定につながることは容易に想像できます。
当時のイギリスは、賄賂が横行する王室や貴族、すべてに敵意を抱く中産階級、絶望した農民からなる腐敗した社会であり、ファシズム全体主義革命による破局か、王による啓蒙絶対主義のいずれかしか選択の道はなかったといいます。
イギリスのバークは、当時、イギリス王ジョージ三世とその顧問たちが、イギリスに啓蒙絶対主義を確立するために、アメリカの13の植民地との争いを歓迎したとみていました。
ドラッカーは、彼らにそこまでの深謀があったとは考えませんが、当時のアメリカの法的地位は茫漠とし、弱小でもあったため、植民地において国王のもとにおける中央集権的絶対主義を確立すれば、本国における国王の力は強大となったであろうと指摘します。手にする資源は膨大となり、威信も絶大となるはずでした。しかも、当時の世界最強の軍隊が、植民地の抵抗に負けるはずはありませんでした。
しかし、アメリカの独立は成功し、イギリスの絶対主義は敗れました。1770年には、イギリスのあらゆるものが啓蒙専制主義に向かっていたいたにもかかわらず、その10年後には、反全体主義が地歩を築いたといいます。国王による絶対主義だけでなくファシズム全体主義も生き残ることはできなくなりました。イギリスでも、統治される者の同意が政府権力を制限するという理念が勝利しました。
当時、アメリカとの戦いに反対していたホイッグ党が政権につき、内閣制度を確立し、内閣の議会に対する責任を明らかにしました。近代政党制度と官僚制度を確立し、王室と議会との関係を定めました。
19世紀のイギリスには自由党と保守党がありましたが、いずれも自由な社会の理念に立っていたといいます。自由そのものに対する本質的な対立ではなく、自由の限界についての対立のであり、官と民の主導権をめぐる対立に過ぎなかったといいます。
ところが、ヨーロッパ大陸における自由党と保守党は、いずれも理性主義であり絶対主義であり続けました。前者は、フランス革命の落とし子であり、真の自由を否定するものでした。後者は、啓蒙専制主義の時代の生き残りであり、反動主義でした。
大陸にも、アメリカの建国の父たちやイギリスのバークに通じる保守主義も存在しました。それは、ロマン主義運動として現れ、科学と芸術に大きな影響を与えたものの、政治的な力をもつことはありませんでした。自由は常に消極的な存在であり、両者の全体主義の対立の狭間で、時折現れる一時的なものに過ぎませんでした。
アメリカとイギリスの普遍的保守主義
1776年のアメリカ独立宣言と1787年のアメリカ合衆国憲法の制定は、その後100年にわたって、法の枠外において諸々の制度の発展の基礎を築きました。
憲法は法的な骨格であり、枠組みに過ぎませんが、その後の制度の依って立つべき理念、進むべき方向、目指すべき目標を明らかにしたことが、真の偉業でした。
アメリカでは、憲法や法律によって社会的な制度をつくり、後の時代を縛ろうとするのではなく、あくまで、自由な社会と自由な政府の原理を発展させるための基礎を用意しました。
二大政党は、伝統や自治を基盤とし、国家権力を目指す集権的体質はもちませんでした。政治家の関心は、あくまで自らの基盤とする地方にありました。したがって、アメリカの政党は、元々反集権であり、国家権力の増大や地方自治への浸食に対しては、常に抵抗してきました。
反面、反イデオロギーであるため、あらゆる政治信条に対して開かれており、人気のあるどのような政策も取り入れる用意がありました。それが、過激な政治運動や政府の絶対主義かを阻んできました。
アメリカにおいては、政治的権力と、社会的、経済的権力との分離が、自由の守り手となったもう一つの制度でした。紳士が政治ではなく企業経営の道に入っていったことが、政治の腐敗の原因ともなりましたが、政治という職業の社会的な地位と評価の低さが、政治と社会の分離を招き、その結果、いずれの側をも絶対の支配階級にしなかったといいます。しかも、政治家の権威の低さのゆえに、自らの地位の恒久化をねらう政治指導者をいつでも拒否できるようになっているといいます。
また、アメリカの政治機能の少なからぬ部分が、地方の自然発生的なボランティア組織によって担われています。この自治の精神は、植民地時代のアメリカにルーツをもつ伝統であり、1776年の理念のもとに発展してきましたが、おそらく世界中でもっとも反全体主義的な存在であり、アメリカの自由を支えているといいます。
アメリカの自由は、開拓地の存在や領土拡大の類が原因であるとする考え方がありますが、ドラッカーはこれを否定します。アメリカの開拓地は、一方で、平等の精神、特に機会の平等をあらゆる人間に与えました。しかし他方で、鉄道、木材、鉄鋼、土地開発など独占トラストの成長を不可避とし、自由に対する重大な脅威をもたらしました。
つまり、アメリカの自由は、開拓地が原因ではなく、開拓地の拡大に伴う弊害や緊張に耐え得るだけの大きさと余力をもっていたということです。
イギリスに自由をもたらしたのは、一般には、議会主権と多数派政府であったとされます。しかし、ドラッカーはむしろ、議会主権と多数派政府をともに制限したこと、さらに多数派の同意による少数派支配を制限したことにあったとします。これを可能にしたものが、野党を政治に組み込む二大政党制であり、内閣であり、官僚機構でした。
多数派による絶対支配を阻止することは民主的でないと批判されることがありますが、少数派の意思もまた国民の意思ですから、多数派による絶対支配を阻止することこそ自由を守ることです。
また、二大政党制によってミニ政党の成立が困難であり、新しい政治理念や政治指導者が大政党において頭角を現さなければならないところに健全性があるとしました。ミニ政党の成立を容易にすることは、少数派の横暴による議会制民主主義の崩壊の危険をもたらすと考えました。
さらに、イギリスの内閣制、特に首相の地位が、政治的権力の分散・制限に寄与したといいます。首相は議会によって選任されますが、二大政党制のもとでは、行政府の長としての権限は、事実上国民から直接与えられていると言えます。このことによって、議会との間に一つの均衡がもたらされます。首相に反対することは、国民に受け入れられる代案を用意する責任が生ずることを意味し、議会で敗れた首相は、直接国民に信を問うことができます。
内閣の政府が、議会の権力と機能から行政に関わるもののほとんどを奪いましたが、首相は自らの政策について議会の承認を必要とすることが、政府に対する厳しい制限となります。
さらに、議会から完全に独立した存在としての官僚機構があります。官僚機構は議会によってチェックされますが、逆に議会をチェックする機関でもあります。継続すべきものの中断を防ぎ、確立された理念に対する議会や内閣による侵害を修正します。
官僚機構には、二大政党のための二つの政策案を常に知ることを期待されるといいます。他方、内閣と議会がもつ予算編成権は、官僚機構における各部門の活動の大枠を定めることにより、官僚機構をチェックし、それに制限を加えます。
ドラッカーは、官僚機構に先見性や独創性を求める意見に異を唱えます。先見性や独創性は議会や内閣の役割だからです。官僚機構は、先見性や独創性が、継続性に関わる基本原則に反しないようチェックする役割をもちます。
ただし、議会、内閣、官僚機構が互いに牽制し合い、権力を制限し合うことに意味があるのであり、官僚機構が政府そのものとなって、議会と内閣の権力と機能との削りつつ肥大化するならば、形を変えた中央集権的絶対専制です。
イギリスとアメリカは、アメリカ独立当時はほとんど同質であったといいます。しかし、アメリカは、独立後の西部開拓の結果、イギリスやヨーロッパからますます遠い存在になっていったといいます。だからこそ、両国において自由な商業社会を発展させた理念の普遍性を際立たせています。
両国は、いかなる人間あるいは集団といえども完全であることはあり得ず、絶対真理、絶対理性を手にすることはあり得ないとの認識からスタートしていました。権力の分離を信奉し、統治を制限するものとして、統治される者の同意と財産権を信奉しました。さらに、経済的領域における支配と政治的領域における統治の分離を信奉しました。
改革の原理としての保守主義の方法論
1776年と1787年のアメリカとイギリスの保守主義は、理念だけでなく方法論においても共通性がありました。実現のための制度的な裏づけのない理念は、社会秩序にとって有害であることを知っていました。ドラッカーは、理念と方法がいずれも正しかったからこそ成功したと指摘します。
その方法には3つの柱があったといいます。
第一の柱は、未来志向であったことです。保守主義というと、過去を理想化し、守り、復活させようとすると考えがちです。しかし、真の保守主義は、自由を生み出し、守ることです。
社会は不断に変化しています。変化している現実を認め、その現実においていかに自由を生み出し、守るかについては、むしろ革命主義的です。制度がもはや変化した社会に適応できていないのであれば、それを改革する必要があるからです。それをせず、過去にしがみつくならば、自由は奪われ、暴力的で絶対主義的になります。
第二の柱は、問題解決思考であったことです。理念においては譲らなくても、制度については、機能し、問題を解決できるものは、イデオロギーにとらわず受け入れました。理想的で完全な制度にこだわるのではなく、基本的な理念のみにこだわりました。
第三の柱は、実証思考でした。人間は不完全であり、未来を予見することはできないため、現実の社会と政治を行動の基盤とせざるを得ません。ですから、理想的で完全な制度を生み出そうとするのではなく、よく知っている馴染みの制度を活用しようとします。より複雑で特別なものではなく、より単純で、安価で、一般的なものを選択しようとします。そして、役に立たなくなった伝統や前例は容赦なく切り捨てます。
社会とは、日々の堅実で地道な営みの結果もたらされるものです。
ところが、産業組織が興隆し、商業社会の制度が通用しなくなりました。そこへ、中央政府が入り込み、中央集権の絶対官僚機構が力をもち始めました。同時に、自治が衰退していきました。
民主主義は、自治や責任ある意思決定のための制度ではなく、責任と意思決定を逃れるための手段になりました。
その結果、民主主義は多数派支配になりました。その後に来るのは衆愚支配です。衆愚支配とは、結局、独裁です。衆愚自身は支配することができませんから、独裁者によって支配されることでしか機能しません。
産業社会において機能する制度をつくるには、産業化前の商業社会に戻ろうとするのではなく、まず、新しい産業の現実を受け入れなければなりません。次に、理想的な万能薬を見つけようとするのではなく、不完全であっても目前の問題に対する有効な解決策を見つけようとしなければなりません。それは、控えめで地味な仕事です。さらに、スタートするのは今の現実からであり、今手にしているものを有効に使っていかなければなりません。