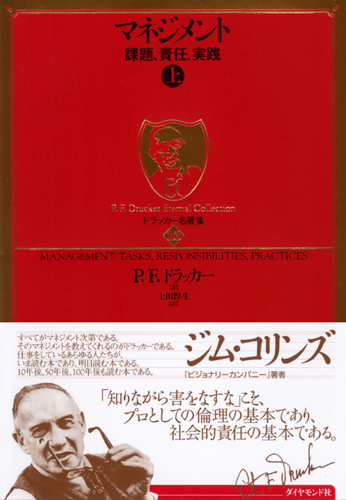過去1,000年にわたる機械と機械文明の歴史は、特定の技術的複合によって特徴づけられ、歴史上の一定時代と対応して、大まかに中世期、産業革命期、現代に分けることができるといいます。
社会学者のルイス・マンフォードは、それぞれの時期を特徴づける技術的複合を、「古技術」、「旧技術」、「新技術」と名づけました。それらの区分を特徴づけるものは、次の4点です。
- 特定地域に起源をもつ。
- 特定の典型的な資源と原材料に依存している。
- 動力を作り出して利用するための典型的手段をもつ。
- 特定の型の労働者を、特定の方法で訓練することによって、特定の才能を発達させ(同時に他の才能の芽をつみ)、特有の仕方で彼らを組織化する。
加えて、各時期は、その社会組織を説明し、正当化するための特定のイデオロギーを形成しました。
古技術期 − 社会的身分としての職人
中世期に相当する「古技術」期は、西暦1000年頃から1750年頃に当たるといいます。主要な原材料は木材であり、主要な動力は風力と水力でした。家畜も使用されました。
地域社会は、封建領主の城によって支配され、保護されていた荘園村落でした。商人階級の出現によって都市が勃興し始めると、商人階級は貴族らと対立を続けながら折り合いをつけていきました。
封建領主に対して商人の地位を維持していくために、商人ギルドが結成され、裕福商人は徐々に貴族の下に位する中間階級となりました。
農民は、土地に縛られる労働から解放され、都市における新しい仕事の中に吸収されるようになっていきました。すると、職人がより重要な役割を果たすようになり、配分者である商人に対抗して生産者を保護するために、職人ギルドが結成されました。
職人ギルドは、公共生活の組織化に大きく貢献しました。仕事の質や仕事に関与する人々の間の経済的平等を維持していくことに絶えず注意を払い、規則に基づいて生産者と消費者の双方を保護しました。各種の学校を経営するギルドもありました。
中世の産業において使用される器械は非常に単純で、職人各人が自分の器械や道具を私有しました。
輩下に徒弟と渡り職人を有する職人を「親方職人」と言いました。徒弟は親方職人と生活を共にし、親方の仕事を助けながら職を身につけました。徒弟の時期が終わると渡り職人となり、同業者内の他の親方職人の下で賃金によって雇用されました。十分な貯えを得た渡り職人は、親方職人として独立することができました。
職人の労働時間はしばしば非常に長かったようですが、自分の意志で多忙なときは働き、休みたいときは休むことができました。自分の家で仕事をし、外へ出たときには互いに面識のある地域社会の人々の間で、職人として尊敬を受けました。
ギルドに属する職人は、労働者の中ではごく僅かで、英国においては全体の10分の1未満であったといいます。残りは農民でした。都市には、組織化されることのなかった臨時労働者がかなり存在していたことになります。
封建社会の組織を説明し、正当化するためのイデオロギーは単純でした。社会は人体に喩えられ、各成員は身分に応じて階級を形成し、その身分に相応しい財産のみを受け入れました。階級間に不平等が存在することによって、固有の役割が果たされ、固有の権利が行使されると理解されていました。ただし、階級内では平等が存在しなければなりませんでした。
宗教の領分と日常生活の領分との間には絶対的な区分がなく、あらゆる行動の領域は、神の摂理のもとにあると考えられていました。あらゆる経済的利益は救済という人生の最大事に従うものであり、個人的な行為と同様に経済的な行為にも、道徳律が拘束力となっていました。
高利貸しは禁じられました。富は人間のために存在し、人間が富のために存在するものではありませんでした。「公正価格」の観念、すなわち、価格は商品そのものの本有的価値に基づき、個人的嗜好とか希少性といった要因で影響されてはならないという考えが存在しました。
実際のところ、物的条件は悪く、神の摂理と言い得るような道徳観念はほとんど実行されませんでした。商業中心地の内部では激しい競争があり、職人と商人との間の階級闘争は日常茶飯事でした。中世後期には近代型の資本家階級が出現し始め、闘争は一段と激しくなりました。
人間関係の領域では、あらゆる身分階層の中で「父」に相当する者(ギルドの親方、荘園領主、教会の権威など)がおり、人々は、彼らの手によって愛され、教導され、保護される代わりに、彼らに対する敬意と服従の態度がとられました。
旧技術期 − プロテスタントと個人主義の台頭
生来の身分が固定された社会は、身分間の移動を制限していましたが、誰しも一定の身分に所属しているという安定感を持っている分、身分の移動の絶え間ない近代的競争社会につきものの精神的不安や危惧の感情は避けられました。
皆が自分の分を心得ているため、社会的移動に固有の欠陥である衒いや虚飾といったものが起こり得る余地が比較的少ないようでした。
身分制社会では異なった身分同士の社会的交流は著しく制限されていたと考えられがちですが、実際は、後の産業社会におけるよりも遥かに交流は容易であったといいます。身分の変更は困難でしたが、交際の自由はあったといいます。これが困難になったのは、フランス革命の影響でした。
社会は、物質的欲求もさることながら、心理的欲求を満足させることなしには存在できません。心理的欲求の中で最も重要なものは、地位と役割に対する欲求です。
成員は、身分の高下にかかわらず、自分がその社会の中でまともな地位を持ち、その社会の存続のために必要な役割を果たしているという感情を抱くことができなければなりません。
産業の旧技術的段階では、巨大な技術的・科学的進歩が見られ、理論的には全人口の物質的欲求を満たすことが可能となり、人類全体の生活水準は向上しました。個人の自由は大幅に増大し、生まれに関わりなく、社会階層を上昇することができるようになりました。
ヤコブ・ブルクハルトによれば、中世において、人間は、一般的カテゴリー(人種、国民、党派、家族、団体など)を通してのみ自分自身を認識していましたが、新しい生活様式によって、個人としての自分を認識するようになりました。
個人主義は、経済的領域における私企業的個人主義の発展と共に、社会的・文化的領域においても発展しました。富の増加に伴って、公正価格および社会的正義の観念も解体し、より精巧な機械や設備のための資本の支出が増大するに従って、ギルドは徐々に崩壊していきました。
それに伴って、人間間の愛情と友情という自然的絆も切断されました。何をしたか、どのようにしたか、あるいは成功したか失敗したかといったことは、すべて個人の問題でした。
「あるものからの自由」を推し進めていくと、個人間の絆は切断され、個人を同胞から分離ないし孤立させていきます。
そこに起こった全体主義的政治集団が、その主張の虚偽性にもかかわらず成功を収めた理由は、分離・孤立した個人に再び地位と役割を与え、社会に結びつけたことでした。それが政治的・軍事的地位と役割であったとしても、人々は感情的安定と同士愛を求めました。
旧技術期の始まりは、1750年頃からとされます。燃料としての石炭の導入、蒸気機関の発達、新しい鉄製錬法の発明などが契機となりました。大規模な生産が可能となり、資本および労働のより大きな供給が求められたため、一人以上の資本家が、設備を持った工場の建設や賃金稼得者の雇用のために、資本を提供しました。
賃金稼得者は、前期の賃金稼得者とは違い、自身が雇用者となることは事実上不可能でした。生まれ故郷である村落社会から、発展期にあった産業都市へ吸収されていきましたが、都市の住宅や衛生施設の構造や効率は低水準でした。
雇用者は、労働者という人間を買ったのではなく、労働力のみを買ったので、労働者の健康や生活条件などの問題は、雇用者の関心事ではありませんでした。使い古されたら容易に取り替えがきく労働者よりも、入手困難であった機械のほうに細心の注意が払われていました。
新しい産業地域は、単一の職業形態の上に依存していましたから、不況が襲うと、その地域のほとんどすべての人々を餓死すれすれの事態に追い込みました。
産業の規模が増大し、工場所有者が個人で資本を提供することができなくなったため、株式会社が現れました。ここに所有と経営の分離が始まり、経営者階級が新たに登場しました。
労働者は、自身の不遇な地位を自覚して立ち上がり、団体交渉のための組合を結成し、労働条件改善のために経営者に対して圧力をかけ始めました。
旧技術期のイデオロギーの一つは、ダーウィンの進化論でした。適者生存の原理のもと、弱者や貧者の救済が反社会的行動であるかのように見られました。経済学における適者生存の原理に相当するものは、自由放任主義であり、人間の自己愛こそは神の摂理でした。
代表的思想家はジェレミー・ベンサムであり、「あらゆる人間行為は利己的なものであり、根本的には、苦痛を避け、快楽を得んとする欲求によって動機づけられる」と主張しました。利己的行為が、長い目で見ると、社会全体の利益になると考えました。
労働者は、賃金による報酬が十分多くなければ、あるいは貧窮が十分不快でなければ、労働という苦痛を引き受けないであろうと考えられました。単に快楽と苦痛に動機づけられて行動する「経済人」の観念が、全産業人の動かしがたいドグマとなりました。
旧技術期における典型的な生活態度は、マックス・ウェーバーが主張したように、その多くがプロテスタントの倫理的表現の中に見い出されます。マルクス主義者も、プロテスタンティズムが本質的に資本主義の思想的代弁であると強調しました。
プロテスタントの信仰が、個人主義の台頭と深く関わっていたようです。プロテスタントは、教会や宗教団体といった媒介なしに、赤裸々で孤独の魂をもって神の前に立つ者でした。宗教は、個人と神との間の個人的な問題と考えられました。
資本家的な商工業者は、ギルドや団体の掟や制約、身分固定の観念や荘園的慣習といったものから解放されたいと望んでいました。公正価格の観念を否定し、商品の価格や労働者の賃金が、自由な市場競争によって定められるべきだと考えていました。
当然のごとく、商人はプロテスタントになりました。それは商業的利益に合致するからではなく、商人はすでに日常生活の諸問題を個人主義的に考えるようになっていたからです。
プロテスタントの信仰の発展と勃興しつつあった商人階級とが結びつき、「神は自ら助くる者を助く」という原理に基づいて、富は神の恩寵の証であり、貧困は罪であるという考えが生まれました。新しい産業家は、怠惰と不道徳と倹約の不足によって自らの状態を招いた人々として、貧者を眺めるようになりました。
この地上での歓楽を求めず、むしろ額に汗して一心に生業に励むという生活様式が生まれました。それまで人間の下僕でしかなかった資本が、逆に人間の主人となりました。ある目的のための手段と考えられてきた貨幣が、目的それ自体となりました。
雇用者に対する労働者の態度は、恐れと軽蔑の入り混じったものでした。人は生きるために自分自身を売らなければならないものの、自分たちの窮乏につけ込んで自分たちを買い入れる雇用者を、心の中では軽蔑しました。
労働は、あらゆる快楽や幸福の反対物でした。仕事に費やされた時間は、その分だけ真の生活から奪われた時間であり、残りの時間を好みのままに生きる権利のために、一定の時間を雇用主に提供するという考え方になっていきました。
労働は他のことをするための金儲けの手段ですから、労働者は自分の仕事の質に責任も関心も持たなくなり、自分の仕事が社会の必要を満たしているかどうかも気に留めなくなりました。
雇用者も本質的には労働者と同じ考えになり、商品が売れさえすれば、その質や有用性などはどうでもよいという考えが一般的になっていきました。
労働者は、責任を与えられなかったがゆえに、責任ある態度を示しませんでした。機械として扱われたがゆえに、機械のように振る舞いました。
監督者から特に睨まれない限り、できるだけノロノロと仕事をしました。あからさまな怠業、あるいは婉曲的な手段によって故意に失策をするようになりました。
これに気づいた経営者は、作業の中に労働者の相違が加えられる余地を残さないような手段を講じました。雇用者は労働者にどんな責任をも分担させようとせず、賃金や福祉の類によってしか、労働者を働かようとする方法を見出すことができなくなりました。
新技術期 − 大量生産の発達と大企業の成長
20世紀初頭に始まった2つの主要な変化は、大量生産技術の発達と大企業の成長です。
大量生産の本質は、機械技術上の原理ではなく、多くの人間をある共通の目的のために組織化する人間管理の原理として考察することができます。
大量生産に従事する労働者の中には、一般的に特殊技能を有している者は必要ありません。人間が受け持つ作業の単位は、一製品ではなく単一の操作ないしは動作であることさえあります。
労働者は、製品と生産手段から完全に分離されました。生産の主体は個々の労働者というよりは組織です。組織を運営するための新しい技能が必要となってきます。これこそ、動機や意欲といった問題に対して大きな関心が向けられるようになった主な理由です。
大量生産は大企業の成長を促します。大企業は本質的に没人間的な構造をもつため、その中で、いかにして人間関係の問題を扱い、人の効果的な統率を実現するかという問題が出てきます。
一国の産業活動の中で、大企業が演じる役割を考察することにも価値があります。産業を社会的組織(人間集団)として典型的に体現しているの大企業だからです。産業が人間という社会的存在にいかなる影響を与えるのかという、いわば産業実験の試験場が、大企業です。
産業の発展は後戻りできませんから、産業上の様々な問題の解決は、過去への回帰によってではなく、新しい産業組織を、諸々の人間的欲求とより密接に調和した形で採り入れることによってこそ、成し遂げる必要があります。