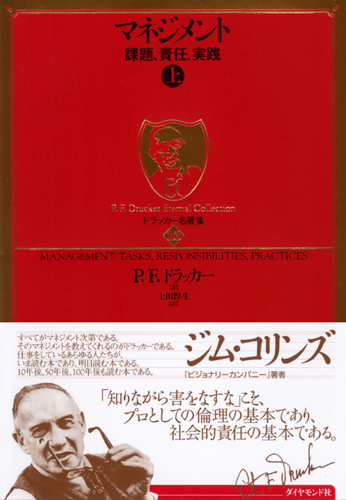「グローバリゼーション」とは、思想や仕組みなどが、国家などの境界を越えて広がり一体化していくことです。ヒト、モノ、カネ、企業などの移動が盛んになり、地球規模での一体化が進みます。
グローバリゼーションに伴う問題は、その支持者がバランス感覚を欠いているところにあります。
グローバリゼーション自体が価値であり、進歩であり、幸福を生み出すから、それを意図的に導入しさえすれば全てうまくいくと考える「グローバリズム」を頑なに信奉するところがあるからです。
「グローバリズム」はイデオロギーの一種であり、「グローバリゼーション」に価値と意味を与え、それを意図的に推進する考え方です。
スティグリッツは、IMF等が自由市場の万能性を極端に信奉し、それに政治的自由主義(政府の介入排除)をも加えて融資の条件として、発展途上国に強要する形のグローバリズムを批判します。
グローバリズムは、グローバリゼーションが一般にアメリカ式資本主義の勝利を認めることと結びついています。発展途上国が成長を望み、貧困を効率よく軽減させるつもりなら、これを受け入れることが不可欠であると決めてかかります。
しかし、アメリカの経験でもグローバリゼーションへの対応には政府が重要な役割を担う必要があることを証明しています。
ところが、途上国に対しては頑なにグローバリズムを押し付け、結果として、貧困の軽減や社会の安定性保持に失敗してきました。
市場の失敗と政府の役割
グローバリズムの背後には、アダム・スミスのモデルがあります。収益を動機とする市場の力は「見えざる手が働いているかのように」経済を動かして、自然と効率のよい結果をもたらすという説です。
このモデルが機能するには条件があり、情報や市場が不備なとき(それは常にといってもいいくらいです。)、見えざる手は全くといっていいほど働かないということです。
つまり、市場効率を改善できる望ましい政府の介入があるということです。政府の主要な活動のほとんどは、市場の失敗への対応です。金融市場への規制、反トラスト法などがそうです。
ところが、IMFの政策は、アダム・スミスの見えざる手が完全に機能するような競争均衡モデルでした。このモデルでは政府が必要とされないので、市場原理主義に基づく「ネオ・リベラル」と呼ばれ、19世紀に一部の人々の間で人気のあったレッセフェール(自由放任主義)政策の復活でした。
そのモデルは失業の存在も否定します。需要と供給は常に等しいので、労働の需要も供給と等しいはずだからです。失業が生じる理由は賃金が高過ぎることですから、これを解決するには賃金を引き下げればいいのです。残るは、仕事をしないことを自ら選んだ人だけだというわけです。
市場制度が機能するには、明確に定義された財産権と、それを守ってくれる法廷が必要ですが、発展途上国では、往々にしてそのどちらも存在しません。
市場制度には競争と十分な情報が必要ですが、途上国では競争が限られ、情報は十分にはほど遠い状態です。
多くの国は市場との仲介を果たす取引機構を持っていて、そこが農民から農産物を買い上げ、国内と国外の市場に出します。この仕組みがしばしば非効率と腐敗の温床となり、農民の取り分を小さくしていることは確かです。
しかし、政府がいきなり撤退したからといって、活気ある競争的な民間市場が自然に生まれるわけはありません。政府の取引機構がなくなると、限られた資本では、この市場には参入できません。
ほとんどの農民は生産物を市場に運ぶトラックを買う余裕すらありません。銀行がないので、必要な資金も借りられません。
ところが、これが儲かる商売だと分かると、そこに地元マフィアが生まれることがあります。政府が撤退することで歳入は減り、農民の暮らしは向上せず、地元の少数の事業家(マフィアのメンバーと政治家)だけが懐を大いに潤すことになるのです。
順序とペース
IMFの数ある失態の中で最も注目されたのは、順序とペースを誤ったこと、そして、全般的な社会状況を認識し損なったことです。
スミスの説に従えば、市場経済が効率的に働くのはすべての前提条件が満たされるときだけでした。ある分野で改革がなされても、他の分野での改革が伴わなければ、むしろ自体は一層深刻化するかもしれません。これが順序の問題です。
しかも、正しく機能する競争的な市場は、一夜にして確立されるものではありません。ですから、ペースも考えなければなりません。
IMFのイデオロギーはそこを無視しています。だから単純に、できるだけ早く市場経済に移行しろと言うのです。
IMFは、セーフティ・ネットが整備され、十分な規制構造が出来上がる前に、近代資本主義の本質である市場心理の突然の変化に国が耐えられるようになる前に、自由化を強要しました。私有財産権が確立されていさえすれば、他のすべては自ずとできてくると主張しました。
社会変革の無視
更に根本的な問題は、市場経済の導入には社会変革が必要であることを認めていないことです。今日の開発経済学が必要だと訴えるのは、広範な初等教育の必要性です。初等教育に投資してきた国は開発に成功しています。
深刻な予算の制約を受けている国のほとんどは、IMFの助言に従って、学校教育を有料にしてきました。僅かな授業料を徴収しても就学率にはほとんど影響しないと統計調査で明らかになっているというのが言い分でした。
ウガンダでは、誰もが学校へ行くのが当然とされる文化をつくることが必要だと考えました。しかし、少しでも授業料を徴収している限り、それが実現しないことも知っていました。実際に、周りの家族が自分の子供をみな学校にやっているのを見て、ほとんどの家族が自分の子供も学校にやることにしました。こうした組織的な変化の力をIMFは無視したのです。
開発の過程で生じる急激な変化は、社会に大変なストレスをかけます。伝統的な権威は危うくなり、伝統的な人間関係も見直されます。そのため、開発に成功するには、社会の安定に格別の注意を払わなければなりません。
ところが、IMFの政策によって不景気が更に悪化し、暴動が相次いで社会構造が破壊されるという事態が頻発しました。十分なセーフティ・ネットがない状態で過度な緊縮財政を強いたため、失業率を高くし、激しい暴動や内紛を起こしました。その結果、投資を招きにくい環境をつくったのです。
機能しないトリックル・ダウン経済学
社会契約の重要な要素に「公平」があります。社会が成長すれば、貧しい者もその利益にあずかり、社会が危機に直面すれば、豊かな者もその痛みを分け合います。
ところが、IMFの政策は、配分や「公平」の問題にほとんど注意を払いませんでした。貧困層を助ける最善の方法は経済を成長させることであると言います。いわゆる「トリックル・ダウン経済学」を信じており、最終的には、成長の恩恵が貧困層まで滴り落ちると言います。
ノーベル賞を受賞した経済学者のアーサー・ルイスは、不平等が開発と経済成長にとって有益であると主張しました。成長の鍵は資本の蓄積にあり、富裕層は貧困層よりも貯蓄に励むと主張しました。同じくノーベル賞経済学者のサイモン・クズネッツは、開発の最初の段階では不平等が増大するが、後の段階になれば逆行すると主張しました。
これらは一つの仮説であり、信条に過ぎません。
19世紀のイギリスでは、国全体が繁栄していたのに、貧困層は拡大したと見られています。1980年代のアメリカでも、経済は成長しましたが、下層の人々の実際の収入は低下していました。
IMFの政策を採用した国では、貧困層が成長から恩恵を受けることはほとんどありませんでした。成長しても不平等は小さくならず、貧困層が減ることもありませんでした。逆に貧困層が拡大する場合もあり、その証拠に都市のあちこちにスラムができました。
他方、日本をはじめとする東アジア諸国は、高い貯蓄率が大きな不平等を必要としないこと、不平等を増大させなくても急速な成長は可能であることを証明しました。これらの政府は、成長が自動的に貧困層に恩恵を与えることはなく、むしろ平等であればあるほど成長は促されると考えていました。
これらの国の政府が行った対策は、賃金の不平等が度を超さないようにすること、教育の機会が全員に与えられるようにすることでした。こうした政策が社会と経済の安定につながり、その安定が今度はビジネスの繁栄する経済環境を生み出しました。
経済成長なくして、貧困の持続的な削減が実現されないのは事実です。しかし、成長が必ずしも全員に恩恵を与えるわけではありません。経済成長を貧困層の救済につなげるためには、積極的なプログラムが必要であると考えられるのです。
成長だけでは国民全部の生活の向上にはつながらないことが分かるようになり、「トリックル・ダウン」という言葉は政策論争の場から消えるようになりましたが、形を変えて生きています。
スティグリッツはそれを「トリックル・ダウン・プラス」と呼びます。成長は、貧困の軽減に必要な条件であり、ほとんど十分な条件であるとし、専ら成長に目を向けながら、ついでに女性教育や社会保障などの問題についても触れておこうというものです。
この政策は、以前と全く同じでした。過度に厳密な調整政策を押し付け、教育費や福祉費を削減させました。タイでは、この結果として売春婦が増え、エイズ関連の支出も切り詰められ、エイズ撲滅プログラムが大幅に後退したといいます。