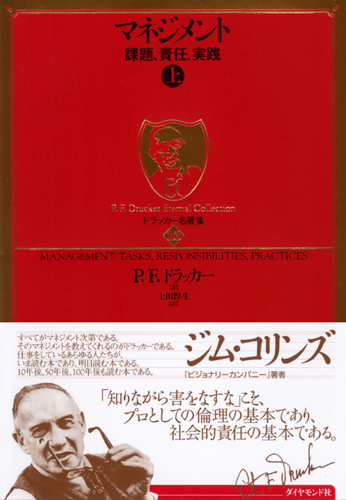組織について議論されるとき、多様な個性を持つはずの個々の人間は、非個性的な要素として扱われがちです。
組織は個々の人間から構成されていることから、まず個人としての人間およびそれに関連する事項について明らかにします。
組織を構成する個人の位置づけについては、次の2つの立場があります。
一つは、個人を単に受動的なものとみなし、選択の自由や意思の自由を否定し、社会的状況が人の行動や思考を支配しているとする立場です。
もう一つは、個人の選択の自由や意思の自由を認め、個人を独立な存在とし、物的で社会的な環境を二次的で付随的な条件とみなす立場です。
バーナードは、協働体系や組織の理論の展開と管理過程の有効な理解のために、この2つの立場を共に受け入れます。
協働や組織は、対立する個々の事象、人間の思考や感情の統合物です。管理者の機能は、具体的行動において、対立する諸力、本能、利害、条件、立場、理想を調整し、統合を促進することです。
個人としての人間の特性
個人としての人間は、単一の、独立し孤立した、独特の全体です。それでありながら、置かれた状況や環境の中で相互作用することによって存在しています。
個人は、内外の状況や環境の不断の変化にもかかわらず、適応力や内的均衡を維持する能力によって、継続性を保ちます。さらに、経験を生かして適応の性格を変える能力も持っています。
個人は様々な特性を持ちますが、そのうち最も重要なものは「活動」です。特に活動のうち観察できる側面を「行動」と呼びます。
行動の中心は、人間間の相互関係における相互作用です。
行動を起こす個人の内部的な要因を「心理的要因」と呼びます。心理的要因は、個人が置かれている状況や環境の中で、過去から現在に至るまで、個人に働きかけてきた様々な要素の影響が合成されて、その内部に形づくられます。
個人に働きかける要素には、物的なもの(物的要因)、生物的なもの(生物的要因)、社会的なもの(社会的要因)があります。
物的要因は、人間の周囲に存在し、人間に影響を与え得るあらゆる物です。生物的要因は、その個人が持つ生物特性であり、性格、能力、体力、才能などを広く含みます。社会的要因とは、他人との相互関係や相互作用によって働きかけるものです。
多様な要因が個人に働きかけることによって、特有の心理的要因が形成されます。しかも、個人は単に働きかけられるだけでなく、働きかけに対して特有の反応や解釈を行い、個人の側からも様々な要因に働きかけ、その反作用を受けるといった経験の繰り返しもまた、心理的要因に合成されていきます。
このようにして、個人はそれぞれ独自の経験や適応性を備えていきます。
バーナードは、人間には選択力、決定能力および自由意思があることを認めます。これによって「自律的人格」という感覚が保持され、社会生活に対する適応力を持ちます。
自我意識や自尊心を持ち、自分のなすことや考えることを重要であると信じ、何事にも創意を持つ人間こそ「協働」に適しています。
しかし、人間の選択力には限界があります。均等な機会があまりに多い場合は、人間の選択力はむしろ麻痺します。
ですから、個人の選択力やその意味を過大視してはいけません。物的、生物的、社会的要因の作用によって、個人の選択の可能性が制約されることがあるのです。
それにもかかわらず、個人が十分な選択力を持つという仮定に基づき、管理者がある行為を行ったとき、その個人がそれに従わないことをもって、意識的に反抗していると誤解することがあります。
実際は、選択力が制限されているために従うことができないことがある、ということを理解しようとしません。このような誤解によって管理活動がうまくいきません。
選択には可能性の限定が必要です。「してはいけない」理由を見出すことが、なすべきことを決定する一つの方法です。意思決定の過程は、主として選択を狭める技術です。
人間の選択力などの意思力を行使し得るように選択条件を限定する方法が、「目的」を設定し、その達成に向けて努力を集中することです。
人間の取り扱い方
本書では、人間を二様に取り扱います。
一つは、個々の人間をそれぞれが独立した存在として取り扱う場合です。でき得る限り一人ひとりの全人格を扱おうとします。
特定の組織の外にあるものとして人間をとらえらる場合が、これに当たります。物的、生物的、社会的要因が独特に個人化した人間として、限られた選択力を持つものとみなされます。
もう一つは、人間のある一つの側面にのみ着目して、集団的に扱う場合です。
組織における特定の協働体系の参加者として人間をとらえる場合が、これに当たります。例えば、管理者、従業員、顧客などという場合、その名称の集団に共通した特定の側面にのみ着目しています。
協働体系の参加者という意味では、その集団特有の協働「機能」に着目していることになります。社会化された (組織の中に溶け込んだ)存在、すなわち「機能的存在」としてとらえています。
この二様の人間は、常に併存していると考えられます。人間が特定の組織から働きかけられている場合、その人は協働体系の外に存在し、独立した個人として扱われています。組織の中で外部に働きかけている場合、協働体系内の機能的存在として非個人化されています。
個人の行動
ある協働体系の外部に存在する人間は、その協働体系に加わるかどうかの選択権を持ちます。その時の目的、欲求、衝動、その人が選択し得る他の機会などの要因が、その選択に影響を与えます。
ある人を協働体系に参加させたい場合、それらの要因のいずれかに影響を与えたり、いずれかを統制することによって、その人の行動を修正しようとします。
人間の欲求、衝動、欲望などを「動機」と呼びます。すでに述べた「心理的要因」と同義です。
動機が行為に先立って明らかであることは稀であり、本人も行為の前に常に意識しているとは限りません。動機は、行為によって事後的に推論されるのが一般的です。
動機は、一般に「求める目的」として表現されます。目的は複数の階層を構成していることが多く、例えば「ある食べ物を手に入れることが目的である」という言い方もあれば、さらに上位の目的として「空腹を満たすことが目的である」という言い方もあります。
したがって、特定の目的は、しばしば一定の条件や仮定があってはじめて求められることになります。
動機によってある行動を起こし、「求める目的」を達成できる場合もあれば、達成できない場合もありますが、その行動は常に「求めない結果」(副作用)を伴います。
目的を達成する過程で他人に害を与えたり、自分の目的達成によって他人が同じ目的を達成できなくなるなどです。商品の販売による収益が目的であったとすれば、経費の支出は目的外の結果です。
「求めない結果」は、些細なもの、やむを得ないものとみなされる場合もあれば、重大な問題となる場合もあります。
個人的行動の有効性と能率
ある行為によって、特定の望まれる目的が達成された場合、その行為は「有効的」であると言われます。
その行為によって同時に生じた「求めない結果」が、取るに足りない些細なものであったとき、その行為は「能率的」であると言われます。「求めない結果」が、達成された目的よりも一層重大であり、それが全体として不満足な状態を生んだときは、その行為は「非能率的」であると言われます。
例えば、ある行為によって商品を販売し、目的とする売上が達成されたときは、その行為は「有効的」です。その行為に支出した経費が、売上に比べて十分に小さかったときは、その行為は「能率的」です。経費が売上と同等であったり、売上を超えたりしたときは、その行為は「非能率的」です。
ある行為によって「求める目的」が達成できなかったものの、別の欲求が結果的に満たされた場合、その行為は「能率的である」ものの「有効的でない」と言われます。
人が求める特定の目的は、物的なものと、社会的なものの2種類からなります。
物的な目的とは、物を手に入れたり、物的な環境や条件を整えたりすることです。社会的な目的とは、他の人々との接触やコミュニケーションや関係を良好にすることなどです。
物的目的の追求が、求めない社会的結果を伴うことがあります。逆に、社会的目的の追求が、求めない物的結果を伴うことがあります。