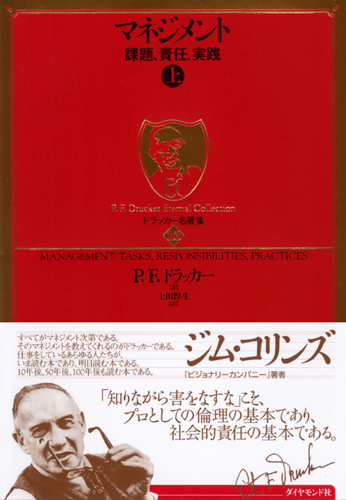中世の人間観では、肉体と霊魂とはそれぞれ独立した存在でありながら、生存中は両者が親密に関係づけられていると考えられていました。
17世紀になると、デカルトが、精神と肉体とは全く異なった実在であると説き、肉体は根本的に一個の機械であるとの見解が開かれました。医学の分野においても、疾病はすべて人間の機械部分の機能障害でした。
フロイトは唯物主義者であり、その理論は、パーソナリティに関する生物学的理論であり、本能の理論に基礎づけられていました。
しかし、人間は社会的かつ文化的な存在であり、本能だけで生きるのではなく、人間関係に関わる社会的欲求をもつ存在です。現代における人間像では、肉体と精神は不可分であり、心理的要因が肉体の病気を引き起こすことが分かっています。
人間のパーソナリティの形成においては、遺伝的資質によるものは一部であり、個人が社会の文化や生活様式に接触するようになって初めて複雑に形成されていくと考えられています。
本能と社会的欲求
中世において一般的であった精神の哲学は、一種の二元論、すなわち、肉体と霊魂とはそれぞれ独立した存在でありながら、生存中は両者が親密に関係づけられていると考えられました。
17世紀なると、デカルトが、霊魂と物体、精神と肉体とは全く異なった実在であり、はっきりとは説明できないような仕方で相互に作用し合っていると説きました。
そこから、肉体は根本的に一個の機械であるとの見解が開かれました。医学の分野においても、疾病はすべて人間の機械部分の機能障害でした。
フロイトは唯物主義者であり、すべての精神活動は将来、医学と化学とによって説明し尽くされると信じていました。フロイトの精神分析学は、パーソナリティに関する生物学的理論であり、本能の理論に基礎づけられていました。
そこから、欧米の産業文明の中に生きる個々人に共通するいくつかの習性は、人間の先天的属性であり、すべての人間に普遍的で不可避的であるかのように信じられました。
「本能」という言葉は、2つの違った意味で用いられます。一つは、中枢神経系の構造によって規定される特定の固定した反応様式に関して用いられます。もう一つは、広く生物学的欲求とか動因(人を行動に駆り立てる力、ドグマ)に関して用いられます。
前者の「本能」は遺伝的に規定され、自動的になされ、知能はほとんど介入する余地がないものですから、経験によってはまずほとんど変えられないとみなされます。この種の行動は、人間や高等動物では消滅してしまっているというのが、最近の生物学者や心理学者の一致した見解です。
後者の「本能」は、性欲、食欲(飢え、渇き)、睡眠欲(眠気)などの欲求です。このような欲求が、人間の行動の原因になると言うことはできます。
しかし、人間が欲求を満足させるためにどのように行動するかを説明することはできません。
欲求を満足させる方法や具体的な行動に関しては、社会や文化の影響を受けます。社会生活は人間本来の生物学的欲求と同程度以上の社会的欲求を生み出すからです。
社会的欲求とは、社会において安定した地位を得たい、優位な地位を得たい、他人から仲間として受け入れられたい、他人から尊敬されたい、他人の役に立ちたいなど、人間関係に関わる欲求です。
人は、社会的欲求の充足に反しない形で生物学的欲求の充足を図ろうとしたり、社会的欲求を充足させるために生物学的欲求を犠牲にすることもあります。愛国的または宗教的自己犠牲などです。
社会が存在するためには、協力の精神に則って人間行動を律するルールが必要です。競争にさえルールは必要であり、ルールの遵守という協力が必要です。
個々人が協力していくためには、社会全体に自らを関連づける立場(地位)と義務(役割)とを知り、相互に意思の疎通ができなければなりません。
個々人は自然環境や宇宙に対しても関係づけられているので、その関係を明確化する思想も求められます。それが、神話、哲学、科学、宗教、その他これらに類したイデオロギーの体系です。
フロイトの誤謬
フロイトは、あらゆる人間行動を説明できる普遍的人間性というものが存在して、それが根本的に生物学的性質を持つと考えていたようです。
人間と社会との間に基本的な二律背反を仮定しました。人間性は根本的に悪であり、人間は生まれながらにして反社会的であるから、社会の役割は人間を順応させることだと考えました。
あらゆる人間行動は、根本において利己的であると前提されます。貪欲、残忍、攻撃性といった否定的感情が先天的で一時的なものであり、愛、友情、寛容といったより肯定的な感情は二次的で派生的なものであると考えられました。
個人は、充足すべき生物学的衝動を満たすために、他の対象との関係に入ります。他人とは、常にある人の欲望充足という目的を果たすための手段です。人間関係は、市場のような交換場所に相当します。
道徳は、人間が生まれながらに持っているわけではなく、社会的相互作用の中で生まれてくるとされます。その過程で、社会は、人間の特性のあるものを強め、あるものを弱めます。
性衝動とその偏向を象徴的な諸目的に振り向けること(昇華過程)によって、文化と呼ぶものが生まれ、人間本能を抑制する(神経症が増える)ほど文化を向上させると考えます。
ところが、人類学者のマーガレット・ミードとルース・ベネディクトは、違った文化を背景として観察した一連の研究によって、人間性が柔軟性に富んでいることを証明しました。
男女間の性的差異にも文化によって違いがあるなど、文化による違いはパーソナリティの全分野に広がっています。ですから、パーソナリティにおける正常・異常の判断は、各文化の内部においては可能であるとしても、多様な文化を横断して普遍的な正常・異常を判断することは困難です。
精神病理学者は、さらに、社会が変化することによって精神異常の型が変化していることも知っています。
幼児は社会の中で他人と接触することを通して、一個の人間として存在するようになると考えることが妥当です。その意味で、社会の基本単位は個人ではなく、第一次集団(内部の個々人同士が直接に関係し合うことができる集団)であると考えられます。
この第一次集団を媒介として、個人は常に、国家や種族というより大きな社会と関係づけられます。
社会の性質
個人にとって最も親密なのは第一次集団であり、家族、遊び友達、近隣の人々、仕事仲間、村の年寄連などが該当します。
第一次集団が、個人に対して社会的連帯と協力のための基礎的訓練を施すことによって、社会的自我と道徳観念との発達に基本的役割を果たします。
どのような社会も、その文化や生活様式は、相互に関係のない要素が継ぎ接ぎされたようなものではありません。各要素部分が相互に関係し合って全体が機能する一個の有機体のようなものです。
したがって、文化の中に新しい特性を導入しようとすると、次のいずれかの反応が起こります。
- 新しい特性が社会の文化に適合し、受け入れられる。
- 新しい特性が社会の文化と衝突し、拒否される。
- 新しい特性が社会の文化に適合するよう修正ないし置換されることによって、受け入れられる。
- 社会の文化と矛盾する新しい特性を強制しようとすると、その社会を解体に導くことがある。あるいは、社会が、解体後に新しい特性を中心として再構築されることもある。解体は、社会で重要な役割を果たしてきた文化的特性を抑制することによっても生じることがある。
社会の習慣、信条、特性などの分化要素は、全体としての文化の中で何らかの機能を果たしており、たとえ客観的な機能を持っていないと思える要素でも、主観的機能を果たしていることがあります。
例えば、労働者階級の特殊な服装、神話、信条などは、経済的成果への貢献の有無が客観的に明らかでなくても、彼らの社会的連帯、経済的な活動力の増大に役立っていることがあります。
したがって、新しい文化的特性が社会に受け入れられれば、必ずその文化全体の構造に何らかの変化を起こすと考える必要があります。
急変する社会
過去にほとんど変化していなかった社会が、ある短期間に急変することがあります。W・F・オグバーンによると、その要因は、機械その他の発明がなされ、普及することです。
発明は、大部分が旧来の諸要素の結合であり、既知の諸原理に依存しています。したがって、文化の中ににそのような要素が多ければ多いほど、新発明の可能性は増大します。つまり、物質文明における技術的進歩は、指数関数的に増大することになります。
このような技術的進歩が不可避的に増大するならば、社会がその変化に適応していかない限り、社会は解体に向かいます。変化に対する社会の適応過程は、次のとおりです。
1.新しい発明や技術が社会に受け入れられる。
2.個々人がそれに反応する。
3.文化的諸制度と信条が新事態を受け入れるべく変化する。
近代の産業技術が社会に及ぼした影響の中で重要ものの一つは、社会的単位としての家族が解体したことです。
牧畜や農業を営む社会においては、家族は単なる生物学的単位ではなく生産単位であり、家族の労働を分担する子どもたちは社会的資産でした。
家族の解体は、社会的資産であった子どもたちを経済的負担とし、出生率の減退と並行するようになりました。
新しい人間観
19世紀の合理主義では、個人や社会は論争や理屈によって変えることができると考えられました。よい思想は、十分に多くの人々の考えを改めさせ、現実化させることができると考えられました。
特定の社会や集団では、権力ある地位にいる人が、法律などのルールを定めるだけで自分の考えを全体的に実現し得る可能性がある場合もあります。
しかし、産業その他の問題の多くが、民主的な社会において生じているため、社会の成員全体の協力によって解決しなければならない性質のものになっています。また、国家を越えた世界的規模に広がっていく場合もあり、一国の権力者にのみ変化を委ねることも不可能です。
安定して調整のとれた社会では、概ね、真面目で勤勉な若者が成功し、不まじめで怠惰な若者が失敗するようになっています。このような社会では、人々は合理的な、つまり、目に見える因果関係の鎖を重視するようになります。
ところが、成功が個人の能力や業績とあまり関係がないように見える社会、特に、大量解雇により経験豊かな熟練者たちが失職するような社会では、人々は、自分の運命が自分ではどうにもならず、ただ運を天に任せるよりほかはないと感じるようになります。
産業社会において個々人が自らの地位と役割を喪失した状態は、まさに、個々人から見て自らの長所や努力と関係がない社会になってしまいます。ギルバート・マリィは、そのような社会こそ、迷信が育つ最良の土壌であると言いました。
現代における人間像では、肉体と精神は不可分であり、感情の緊張が長引くと、肉体の構造が変調を来して、生命にさえ関わるような病気(精神身体病)を引き起こすことが分かっています。産業上の災害もまた、心理的な動機によって起こることが知られています。
産業組織内に起こる憤慨、心配、恐怖、憎悪などの感情が人々を不幸にし、神経質にするだけでなく、時には生命をも縮めてしまうことが理解されれば、産業組織内の人間関係の問題は更に重要になってきます。
パーソナリティの理論
遺伝による個人の心理的素質は、比較的単純な性質を持つと考えられています。
パーソナリティの一般的な形成は、個人が社会の文化や生活様式に接触するようになって初めて複雑に形成されていくと考えられています。
ただし、人生の初期においては、文化は、家族という媒体を通して子供に影響を与えます。
したがって、同一文化におけるパーソナリティの個人差は、個人の資質や知能の遺伝的差異と、家族による育て方や家族構成の差異によると考えられます。
個人のパーソナリティは、遺伝的特質と、家族を媒介として与えられる文化との相互作用の結果生じることになります。
人間には、飢え、渇き、その他の生物的衝動といった第一次的欲求がありますが、幼児は全く無力の状態にあるため、他人の助力なしにそれらの欲求を満たすことはできません。ですから、幼児期には、愛され、保護され、面倒を見られたいという最も基本的な心理的欲求が起こります。
この欲求から「人間は他人に依存しなければならない」という意識を抱くようになり、幼児期以降の社会的地位を求める欲求につながるといいます。個人の社会的地位は、社会集団に帰属している証であり、感情的安定の徴でもあります。
個々の文化は、その全体的状況の上に立って、人間に特定の行動形態を促します。個々人は、仲間からの承認や好意を得るために、この特定の行動形態を利用します。このようにして、社会の文化が個人のパーソナリティに影響を与えていきます。
人間の基本的なパーソナリティは5歳までに決定されると言われますが、この期間を通じて、父母や兄弟たちに対する態度が形成され、それ以後に接する人々に対する態度の原型となります。
人が身につけていく性格は、人生のごく初期において自然的に学び取られ、その自我の中に組み込まれた特性です。つまり、その人が子供の時に置かれた特定の状況の中で最もよく働き、かつ最大の効果をあげた特性であったと言えるものです。
基本的パーソナリティと社会的パーソナリティ
子供は自己を両親と同一視することによって、両親の道徳律の一定の側面を自分の心の内部に受け入れ、「上位自我」(内在化された社会の声で、無意識的なもの)を形成すると言われます。
これは良心にも似た「静かなささやき声」であり、統制力としては「微弱」であり、統制の範囲も限られているとされます。
このようにして人生の初期に獲得された特性は、自我の深層に根ざし、個人のパーソナリティの中核を形成しますので、容易に変えることはできません。逆に、変化に対する抵抗を示すと言われます。
これは「基本的」パーソナリティと呼ばれます。
例えば、内向的か外向的か、控え目かやり手か、自信が強くて楽観的か自己反省的で悲観的か、強気か弱気か、独立心が強いか依頼心が強いか、寛大か狭量か、几帳面かだらしないか、など一個人を他人から十分に区別させるような特性です。
他方、パーソナリティにはより表層的な側面もあり、「周辺的」、「公共的」あるいは「社会的」パーソナリティと呼ばれます。基本的パーソナリティが形成された後に、個人が社会から直接的に影響を受けることによって形成されます。
社会的パーソナリティは、基本的パーソナリティに比べて、変化しやすいと言われます。
ある職業に従事すると、その職業集団において一律に課される行動規範の影響を受けます。それは一つの機能あるいは社会的役割であって、性格的特性ではありません。そのため、同じ人が職場、遊び仲間の集団、あるいは家庭で、それぞれ別人のように振る舞うことはよくあります。
社会的パーソナリティの変化のしやすさは、人間が社会的パーソナリティの側面において順応的であると言い換えることができます。
この点から、個々人としての行動よりも集団の行動のほうが変わりやすいという事実が導き出されます。