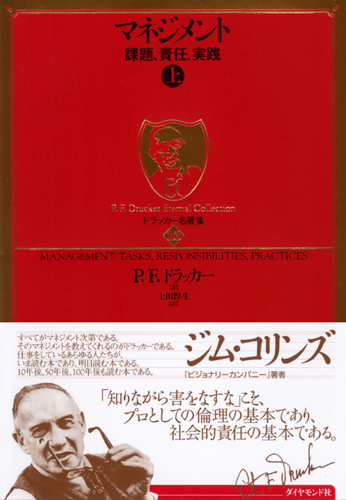産業組織における人間問題の具体的状況を調査するため、ウェスタン・エレクトリック株式会社のホーソン工場で、1924年から1932年まで数々の調査が行われました。
この長期的調査の結果は、分かってみれば単純で当たり前の事柄でしたが、経済学を支配していた基本的な人間像(経済人モデル)とは異なる本来の人間像に立ち戻ったという意味で、レスリスバーガーは「健全なる常識への復帰」と表現しました。
従業員の行動を感情から切り離して理解することはできません。従業員の感情に大きな影響を与えているのは、経営組織内に事実上存在する社会的組織である「インフォーマル組織」です。
ホーソン調査の概要
ホーソン工場では実に様々な調査が行われましたが、ここでは3つの実験を紹介します。
照明実験
始まりは照明実験です。照明の質と量とが従業員の作業能率に与える影響を調べることが目的でした。
従業員が2つのグループに分けられました。一つは「テスト・グループ」と呼ばれ、様々な照明度のもとで作業を行いました。もう一つは「コントロール・グループ」と呼ばれ、一定の照明度のもとで作業を行いました。
最初の実験期では、テスト・グループの照明度を3段階に高めたところ、生産高が上昇しました。ところが、コントロール・グループでも同程度に生産高が上昇しました。
次の実験期では、テスト・グループの照明度を下げたにもかかわらず、生産高は上昇しました。同じく、コントロール・グループでも生産高が上昇しました。
更に次の実験期では、照明度を一定につつ、従業員には「照明度が増大していく」と説明しました。すると、従業員は「本当に照明条件が改善された」と満足の意を表したものの、生産高にはほとんど変化がありませんでした。次に、照明度を一定にしつつ「照明度が低下していく」と説明したところ、「照明が乏しい」と不平をこぼしましたが、生産高にはほとんど変化がありませんでした。
最後に、照明度を月光レベルまで徐々に下げていったところ、生産高にほとんど減少は見られませんでした。
実験の結果から、照明と作業能率との間に相関関係を見出すことは不可能でした。実験は失敗であったと結論することもできたかもしれませんが、調査員たちの一部は、当初の仮説を疑いました。
継電器組立作業実験
次に計画された実験は、他の従業員から分離された単独のグループが、様々な作業条件のもとで仕事をし、生産高を測定するものでした。
実験中は、作業態度が入念に観察されました。従業員の食事や睡眠時間などもすべて記録され、定期的に身体検査も行われました。実験は5年にわたって行われました。
その結果、物理的環境の変化と生産高との間に、統計的に有意な相関関係を見出すことはできませんでした。
実験の最初のほうでは、作業条件を改善する方向での変化を加え、生産能率が上昇していくことを確認したため、仮説が実証されつつあると感じていました。
従業員は、作業条件が改善されて生産能率が上がると給与も上がること、自分たちが会社の経営陣たちから注目されているらしいと感じることが幸福でした。
ここで、作業条件をすべて元の状態に戻すことが提案されました。現状からすれば作業条件が改悪されることを意味しましたが、生産高はきわめて高い水準を保ち続けました。
改めて調査員たちは、人間的状況がきわめて複雑な性質を持つことを思い知らされました。被験者になること自体が従業員にとって意味を持ち、物理的環境の変化では収まらない様々な変化を引き起こしました。
今回の実験では、物理的諸条件のみが生産高を左右する原因であることを確かめるため、従業員たちがいつものと変わらない感情をもって仕事についてくれるよう、様々な配慮が行われました。重役室を使用しての従業員との話し合いが度々行われ、実験計画自体に従業員の意見を反映させました。従業員たちの保健や福祉が重視され、その意見や希望や心配事は入念に究明されました。
このような配慮は、作業条件の変化を超えて、これまでの作業の監督方法を根本から改変したことを意味しました。この点にこそ生産能率向上の原因がありました。
面接実験
これまでの実験が示唆したことは、従業員の態度や感情の重要性でした。作業条件だけでなく、従業員がその条件をどのような意味でとらえるのかによって、従業員の態度や感情などの反応が決まるということです。
従業員がその組織のために働く意欲を持つかどうかは、その従業員が自分の仕事や同僚や上司に対して抱く感情によって決定的に左右されます。その感情に影響を与えるのは、客観的な環境や条件そのものというよりも、従業員がそれらに見出す意味です。自分にとっての意義です。そこには従業員個々の感じ方、内的思考、先入観、好悪感などが関わるため、同じ環境や条件が、それぞれの従業員によって異なる意味を持つこともあります。
調査員たちは、調査の方針を大きく転換することにしました。論理を捨て去り、謙虚な気持ちをもって現場に入り込み、従業員に自分の関心事を直接語らせ、語り尽くせない事柄を理解するため、面接実験を行いました。
当時としては画期的な着想でした。人が話している言葉を最後まで聞かないうちに遮らないこと、最後まで注意深く聞くこと、相手に対して忠告めいたことは口にしないこと、道徳的価値判断をしないこと、議論しないこと、如才ない態度を取り過ぎないこと、自分独りでいい気になって話さないこと、誘導質問を避けることなど、今では当たり前の注意点について、失敗を繰り返しながら少しずつ学んでいきました。
話してもらうべきことは、聞き手にとって重要な事柄ではなく、話し手にとって重要な事柄です。仕事上の動機づけに関わることを聞きたくても、そこに影響を与えている原因が、仕事に直接関わることであるとは限りません。その点は、聞き手に分かることではありませんし、話し手が本当の原因に気づいていないことさえあります。
面接を繰り返していくと、同情的で熟練した聞き手に対しては、従業員は心の中にある最も重大な事柄を明らかにしてくれることが分かりました。重要なのは、聞き手と話し手の間の信頼関係です。それを裏切ってはなりません。話し手が話した内容によって、後々迷惑が返ってくるようなことがあっては絶対にいけません。
本来の人間像
実験開始当初、調査員たちは、個々人の満足感とその直接的作業環境との間に論理的相関関係を発見できると信じていましたから、不平の種さえ取り除けば直ちに不平は消えるだろうと考えていました。ところが、実際は、それほど単純ではありませんでした。
いわゆる「不平屋」と呼ぶべき人たちがいました。不平の対象となるべきものを取り除いても、次々と新たな不平が出てくるような人たちです。
不平の対象となっているものに全く手を触れないでいたにもかかわらず、数回話を聞いただけで、不平がなくなってしまう人もいました。何もしていないのに、不平が改善されたと喜ぶ人さえいました。
このような人たちが求めていたものは、同情ある聞き手に憂鬱の種を聞いてもらうことでした。
分かったことは、感情を持つ人間を扱う上で経験的に理解されてきたことと同じでした。従業員の行動を感情から切り離して理解することはできないということです。この場合の「感情」は、単なる気分や情緒だけでなく、忠誠や誠実や連帯などの気持ちを含んだ広い意味です。
感情は簡単に偽装され、同じ感情が様々に異なった形式で表現されます。合理化されたり、客観化されたりすることもあります。自分がそう感じているということではなく、事実客観的にそうであるという言い方です。例えば、「私はあの人が好きではない」ではなく「あの人はそもそも悪い人だ」といった言い換えです。
人間の感情を支える全体的状況
感情の表現は、その人の全体的状況に照らさないと理解できません。
例えば、従業員の周囲で一つの物理的変化が起こったとき、直に従業員の反応を起こすのではなく、従業員がその変化を受け止める態度によって意味づけされた上で反応を起こしているということです。
そこには感情が関わりますから、論理的な反応ではありません。意味づけに影響を与えるのは、その人の社会的学習(その人が属する社会集団において身につけた習慣による学習)によって抱くに至った感情(価値、希望、憂慮、期待など)です。
さらに、その人が属している職場の仲間や上長との社会的接触を通じて得ている人間的満足にも依存します。
集団の感情
人は孤立した存在ではなく、過去や現在において、いくつかの集団の成員です。各集団での協同活動の中で、成員が相互に様々な気分や感情を抱き合うことによって結束が生まれ、集団の感情が形成されます。
ですから、個々の事象は、それ自体でのみ取り扱うことはできず、集団における社会的価値を担うものとしても解釈される必要があります。
社会的行動の一表現としての生産高
ホーソン調査において行われた実験の一つに、バンク捲取観察実験があります。
この作業には、捲線工、ハンダ工、検査工の3つの職種集団があり、集団請負制で仕事に就いていました。働いて生産高が上がれば上がるほど報酬が増加するようになっていましたから、生産高をできるだけ高くするよう互いに刺激し合うことが予想されました。
ところが、実際には、次のような感情が働いていました。
- 仕事に精を出し過ぎてはいけない。さもなければ「がっつき」とみなされる。
- 仕事を怠けすぎてはならない。さもなければ「サボり屋」とみなされる。
- 仲間の誰かが迷惑するようなことを上長にしゃべってはならない。さもなければ「つげぐち野郎」とみなされる。
- 他人におせっかいをしてはならない。たとえ検査工であっても、検査工ぶってはならない。
個々の従業員が集団の成員であるためには、その集団の基準に従わなければなりません。集団員の一人が一日の作業量として適当とされている基準以上に働くと、その人を基準に服従させるような社会的圧力が加わりました。
従業員ごとの作業量の差は、個々人の知能や技能の差とは無関係でした。そこには強力な人間感情の作用が働いており、集団内のインフォーマルな地位が反映されていました。生産高を決めているのは経済的動機ではなく社会的動機であり、人間関係に関わる感情が動機になっていました。
感情に影響を与えるインフォーマル組織の存在
会社には、組織図で表現されるフォーマルな組織の中に、組織図で表現されないインフォーマルな組織が存在していることが明らかでした。しかも、インフォーマルな組織は、個々の従業員に帰属感を起こさせ、単一体のように振る舞わせる信念や信条を持ち、従業員に自動的に協力を要求するような社会的な掟や規範を持っていました。
インフォーマル組織の行動規範や掟は、会社の技術的・経済的目的と一致するとは限りません。インフォーマル組織は一つの会社内に複数存在することも多く、互いに対立し、分離させようとする力が働くこともあります。
多くの人々は、友人や職場の仲間から立派な人として認められることによって得られる満足を望んでおり、金銭は、このような社会的承認の全体から見て、ほんの僅かな部分にしか当たらないことが明らかになりました。
上役から挨拶される仕方、新参者の援助を頼まれること、難しい仕事の監督を頼まれること、特殊な技能を必要とする仕事を与えられることなどは、すべて社会的承認の行為であり、作業集団の中で自分が占めている位置を教えてくれるものです。
人は、自分が社会的重要性を持つことを具体的に知りたがっており、社会的に有用と認められている技能を身につけたがっています。経済的な安定感よりも、集団の重要な一員であることによって得られる安定感のほうを強く望んでいます。
労働争議の争点には、賃金、労働時間、物的作業環境などの問題が掲げられますが、背景に人間的状況に関わる感情の問題が隠れており、それが表面的に偽装された形で現れている可能性があります。その部分の理解がなければ、根本的な解決には至りません。