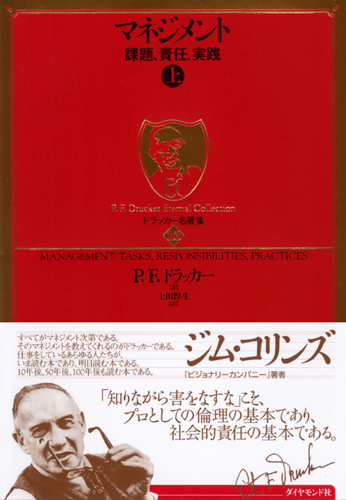リチャード・ルメルト(Richard P. Rumelt)は、戦略論と経営理論の世界的権威で、ストラテジストの中のストラテジストと評されています。
この記事では、『良い戦略、悪い戦略』(GOOD STRATEGY, BAD STRATEGY)および『戦略の要諦』(The Crux: How Leaders Become Strategists)を基に、ルメルトの戦略論を概説します。
今日では様々な分析ツールが出回っています。そうしたツールは、フレームワークを当てはめ、データを収集し、分析や比較を通じて問題点や失われた機会を洗い出します。
注意しなければならないのは、どのツールもいくつかの前提を置き、注意すべき要素を最小限に、ときには一つに絞り込むことによって分析の効率を上げていることです。その前提が、直面する状況に適合しているとは限りません。
複雑な状況の診断に白黒をはっきりさせてくれる切れ味のいいツールはいかにも有効に見えますが、判断を誤らせ、見当外れの結論に導いてしまうこともあります。
投資意思決定ツール
何らかのプロジェクトや設備投資が提案された場合、その便益と費用を対比させて評価する手法は、一見して理にかなっているように思われます。
将来キャッシュフローを推計し、それを現在価値に割り引きます。現在価値がプラスであれば、プロジェクトを承認してよいと教えます。
投資意思決定ツールで考慮されるリスク要因は、経済的リスク、競争の脅威、プロジェクトに直接関連するリスクであり、それらに伴う将来キャッシュフローの不確実性が考慮されます。
しかし、このやり方を忠実に実行している企業はごく僅かであるといいます。
多くの企業では、マネジャーにプロジェクトを立案させ、その成否の見通しについてシニアマネジャーが検討するというスタイルをとっています。必要に応じて信頼できる顧問の助言を受けます。その際に重視されるのは現在価値ではなく、競争状況、成長見通し、タイミング、自社の能力などです。
このようなスタイルの決定方式では、プロジェクトの立案者と意思決定者が異なり、立案者は知識やリソースの決定権を掌握していないので、戦略プランニングはリソースの分捕り合戦になりがちです。
そのような場面では、自分のプランをよく見せるために、都合のよいデータの利用やデータの改ざんを行う動機が生まれます。面倒な手続きによって組織内の知識や能力を十分に活用することを避けるようになります。
企業規模が大きいと、経営幹部でさえリソースを競い合う戦略やプロジェクトの全体像を把握していないことが多いので、どうせ分からないだろうと思ってしまうのです。
そうなると、戦略のクオリティは、関わる人間がどれだけ誠実で私利私欲に惑わされないかに左右されることになります。
結局、提案者の能力不足または不誠実こそが、長期投資における最大のリスクであると言えます。
そもそも担当者自身の金が懸かっているわけではありません。プロジェクトがうまくいかなくなったとしても、最初に気づくのは当の本人ですから、ばれる前に逃げ出し、残された人間がプロジェクトを台無しにしたと避難されることになります。プロジェクトがうまくいけば組織内の立場は強まり、より多くの権限と報酬を手にするか、他社へ好条件で引き抜かれるでしょう。
意思決定を行う取締役会のメンバーは、特に遠い将来の利益に関して数字の操作がよく行われることを承知しており、将来利益の見通しは割り引いて聞くようになっています。
また、複雑で高度な分析の中に埋め込む形で数字の操作が行われる例が多いことも知られているので、高度な分析から得られた結論は眉唾だと感じ、自分たちの直感を信じるようになります。
しかし、そうなると、意思決定は直感的な駆け引きのようになってしまい、外部のデータや分析に頼らなくなるという近視眼的な対応が根付きかねません。
このような問題は「エージェンシー問題」と呼ばれます。組織や人間関係を依頼人(プリンシパル)と代理人(エージェント)の関係性として捉えるものです。依頼人と代理人の利害は常に一致するとは限らず、しばしば利害対立が起こります。
この問題の解決は難しく、投資意思決定の場合には、事後的な解決、すなわち結果に対して代理人に説明責任を負わせること以外によい案はなさそうです。
しかし、結果が出るまでには長期間が必要ですので、流動的な組織と早い出世を狙う経営幹部の前では役に立ちません。
こうした理由から、長期プロジェクトにおける投資リターン評価に関する経済理論は、無視されがちになります。経営陣が求めるのは投資資金の早期回収なのです。
理論は、部下の無能力や誠実や出世志向を無視しているだけでなく、経営幹部自身のボーナスや短期的な業績を重視する傾向をも無視しています。
BCGマトリクス
プロジェクトを提案するマネジャーが、最終決定権を握る上層部に信用されないとき、ゲームのルールを変え、当初提示された分析を超越するような強力なツールが求められます。
そうしたツールの一つが、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が開発した「成長率・市場占有率マトリクス」です。このマトリクスによる分析は「PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マトリクス)分析」と呼ばれます。
企業の長期戦略を考えるためのフレームワークで、自社の扱う複数の製品・事業の組み合わせと経営資源配分を最適化するために使います。
マトリクスは、縦軸に市場成長率、横軸に相対的市場占有率をとり、自社の事業や製品を4つの象限に当てはめていきます。
市場成長率と相対的市場占有率が共に高い事業・製品は「花形(Star)」です。市場成長率が低く、相対的市場占有率が高いものは「金のなる木(Cow)」です。市場成長率が高く、相対的市場占有率が低いものは「問題児(Question)」です。市場成長率と相対的市場占有率が共に低いものは「負け犬(Dog)」です。
各事業・製品のマネジャーが難解で高度な分析を持ち出して、自分たちの事業・製品の予算増額を主張するとき、個別に投資意思決定をしようとすると、先に取り上げたような経営幹部の能力や誠実さの問題を考慮せざるを得なくなり、最終的な意思決定と予算の配分は困難になってきます。
ところが、事業・製品をBCGマトリクスに位置づけると、事業・製品の関係が明らかになり、なすべき意思決定の方向が明確に示されます。明らかにゲームのルールが変わったのです。
投資意思決定ツールであれ、BCGマトリクスであれ、どのフレームワークも事業や経営のある一面を重視します。どれを使うかによって、組織内の位置づけや力関係は変わってきます。
投資意思決定ツールを活用するとなれば、財務分析に長けた人間が有利になりがちです。BCGマトリクスを使う場合には、どの事業が「負け犬」かを決定できる経営陣が優位を取り戻します。
ジャック・ウェルチの改革、すなわち、業界でナンバーワンかナンバーツーになれなければ、再建、売却、閉鎖するという方針も同様です。ウェルチの就任当初、社内には高度な重層式の戦略プランニング・システムが存在しましたが、それをあっさり超越したわけです。
BCGマトリクスはブームになり、なぜこれを使うのか明確に意識せずに使われていましたが、実際には投資意思決定ツールを超越することが最大の動機だったわけです。
破壊的イノベーション理論
この理論も、むやみに使われた結果、「破壊」という言葉が、既存事業さらには現状を覆すようなもの全てを指すことになってしまっているといいます。
この言葉を最初に使ったのは、「イノベーションのジレンマ」で有名なクレイトン・クリステンセンとジョセフ・バウアーです。競争相手が新技術を市場に投入したときに、それまで業界トップだった企業がその地位から滑り落ちてしまう現象を指していました。
圧倒的なシェアを握っている企業は既存顧客を大切にします。特に大口顧客や要求の多い顧客は既存製品の大型化・高性能化を求めることが多く、それに答えているうちに、多少性能は劣るものの安価な技術(破壊的技術)が登場していることを見落としたり、軽視したりてしまうのです。
経営者たちは、成功した製品や重要な顧客に固執し過ぎているのではないかと心配し始めました。
クリステンセンは、破壊的技術は低価格で、少なくとも当初は性能も劣る製品の形で出現することが多いと言いましたが、実際はこれと正反対の事例も珍しくありません。例えば、iPhoneは典型的な高価格・高性能の破壊的技術でした。
業界の主力企業が重要顧客にフォーカスし過ぎるとか、低価格・低性能の破壊的技術を見落とすといったクリステンセンの主張は、追加的な研究では支持されていないといいます。
それでも、有力企業が小粒のライバルや新参者や新技術に敗北を喫して業界から押し出されるケースは決して珍しくありません。
そうしたケースでは実際に何が起きているのか、破壊的技術の実例に着目すると、貴重なヒントを得ることができます。
例えば、コダックは、特定の企業の特定の製品に負けたのではなく、写真を撮影しデータとして共有するエコシステム全体に負けたと言えます。ブリタニカ百科事典も、コンピュータとウェブによるエコシステム全体に負けました。
敗北した企業は決して破壊的技術の出現を見落としたわけではありません。ルメルトが指摘する真の問題点は次の通りでした。
- 対応には膨大なコストがかかり、それに値するようには見えない。
- 対応に必要な技術力、財務的な体力、組織体制が備わっていない。
- 現在のエコシステム全体を破壊してしまう。
1.の場合、新技術に手を打とうとすると蓄積された利益をかなり取り崩さなければならないため、即座に対応する価値があるのかと懐疑的な意見が出て、様子見の費用便益分析が行われます。
ルメルトは、事業を多角化していない場合、思い切って身売りしてしまうほうがよいと言います。
2.のうち、技術力に欠ける場合は、必要なスキルを備えている会社を買収するのが定石です。これまで起きた破壊的イノベーションによる大型倒産は、買収する企業がない場合に起きたといいます。
このような場合の最善の戦略は、おそらく必要なスキルを備えた合弁事業のパートナーを探すことです。それができなければ適切な相手に事業自体を売却するか、ぎりぎりまで衰退事業の延命策を図ることです。
技術力の不備よりも、組織としての柔軟性に欠けるためにすぐに手を打てないケースのほうが多いようです。長年一つの事業に特化してきた企業や頭の硬い幹部がいる企業がそうなりがちです。この場合にも買収はよい解決策となり得ますが、買収した会社はその無能の幹部から遠ざけておくべきです。