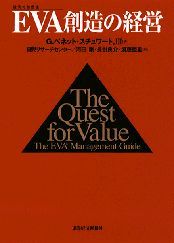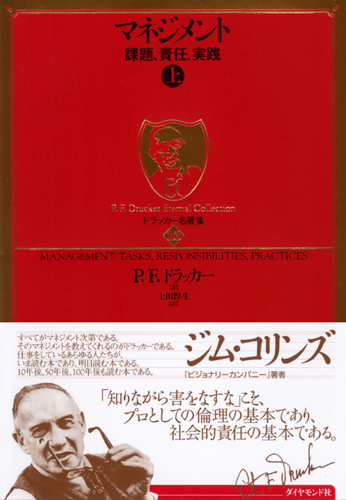情報革命あるいはIT革命と言われて久しいですが、その革命はとどまるところを知らないようです。IoTやAIなどは現在も急激な進歩の中にありますが、その中心は、技術革命の延長にあるように見えます。
しかし、ドラッカーは、「新しい情報革命」を標榜していました。それは、技術革命ではなく、情報の意味を変える革命です。技術、機械、手法、ソフトウェア、あるいはスピードを争う革命ではななく、情報のコンセプトに関わる革命です。
情報革命の主導原理
これまでの情報革命の焦点は、技術であり、ツールでした。中心はデータであり、データの収集、蓄積、送信、ディスプレイが中心でした。つまり、いかに情報を大量かつ高速に処理し、整理・分析し、美しく表示するかというものであったと言えます。
技術やツールは高度化・高速化し、ストレージは大容量化したため、膨大な情報を素早く処理し、蓄積できるようになりました。その結果、扱うデータや放出される情報も膨大化し、溢れかえるようになりまた。人間に余力が出るどころか、情報に追い立てられ、ますます忙しくなりました。
しかしながら、ITは、企業をはじめとする組織において、今のところ、トップマネジメントに対し、情報ではなくデータを提供するにすぎません。新しい問題意識や新しい経営戦略を与えるには至っていません。そのデータは、せいぜいのところ、コストの実態を示す会計情報のレベルに過ぎないと、ドラッカーは言います。
ドラッカーは、過去においても、情報革命と呼べるものが3度あったと言います。文字の発明、書物の発明、印刷の発明です。これらは画期的な発明であり、情報を伝達する道具の発明でした。
先に述べた現在の情報革命についても、過去の情報革命と比較してみると、その位置づけがよく分かります。情報技術者は道具職人であって、印刷職人に当たる者です。技術が発明された当初は、道具職人は賞賛され、尊敬されます。それだけの貢献をしていることは間違いありません。いつの時代も技術の進歩は偉大な業績です。
道具職人は、その道具を整備し、性能を上げ、普及を促進します。しかしながら、それが一定のレベルに達して十分に普及すると、人々の関心は道具から離れていきます。印刷技術が発達して誰もが安価に整った装丁の聖書を手にすることができるようになったら、今度は、聖書以外のものを読みたくなるはずです。
つまり、人々の関心は、道具から情報の中身、情報が持つ価値そのものに比重が移ります。いかに複製し、伝達するかではなく、その中身の方が重要になります。それこそが、ドラッカーが指摘する「新しい情報革命」です。
ITは出版物を駆逐するのか
情報技術あるいはインターネットが出版物を駆逐すると言われました。新聞を駆逐し、テレビや映画にとって代わるとも言われました。
しかしながら、ドラッカーの言う「新しい情報革命」を前提に考えれば、そこには勘違いがありました。実態は逆であって、ソフトがITを占領しつつあるわけです。情報技術あるいはインターネットはソフトを生み出しません。価値あるソフトが新たな媒体を活用しつつあるだけです。
ところが、そのように取って代わられると言う人たちは、道具にとらわれていました。現在の道具がすべてであると思っていたわけです。
最近では、そのような状況も変わりつつあるようです。出版社も新聞社も、あるいはテレビ番組や映画の制作者も、自分たちの仕事は情報の中身を生み出しているということを理解しつつあるようです。
ただし、道具にのみ価値を見出し、道具にのみ自らの仕事を見出してきた人たちは、自らが生み出してきた価値が何であったのか、今後いかなる価値を生み出すべきなのかを考えなければなりません。
もちろん、情報の中身が重要であるからといって、同じ中身をただITに移植すれば済むわけではありません。媒体の変化は内容に影響を与えます。顧客層が変化し、顧客が求めるものも変化するからです。
既存の事業を行っている者は、この変化になかなか適応できません。手段であった道具も含めて過去の成功にとらわれているため、その成功を捨てることができません。その間に、まったく予期せぬところから、予期せぬ競合が現れ、市場を一気に独占していくということが起こるわけです。
経営における新たな情報革命
組織の経営において重要となる新たな情報革命は、顧客にとって新たな価値を創造するものでなければなりません。顧客にとっての価値を創造することこそが、真に事業を成功させるものです。
経営において価値を創造するものとは、事業の定義、新しい現実に基づく経営戦略、体系的廃棄、イノベーション、利益とシェアのバランスなどに関して、リスクを伴う意思決定を行うことです。
道具である情報技術は、それらの意思決定に必要な情報の提供に貢献できなければなりませんが、意思決定を行うのは、人であるマネジメント、特にトップマネジメントです。道具によって代替されるものではありません。
また、道具が自動的に必要な情報を提供してくれるわけではありません。道具が処理し、提供できるのはデータに過ぎません。道具職人である情報技術者は、道具を整備し、「どのような方法でデータを処理するか」に力を発揮することはできますが、「どのような情報を生み出すべきか」を決めることはできません。
それを決めることができるのは、情報を活用し、意思決定しようとするマネジメントしかいません。
ですから、価値を創造するための情報革命において問題となるのは、情報の内容、すなわち情報の意味と目的です。情報についての新しい定義であり、新しいコンセプトです。
そこから、情報の助けによって行うべき仕事と、それらの仕事を行うべき組織のあり方を明らかにしていくことができます。つまり、情報に基づき事業を定義し、戦略を構築し、仕事を決め、組織をつくります。
活動基準原価計算(ABC)の導入
経営における新たな情報革命をまず主導したのは、会計の分野であったと言います。具体的なものとして、ドラッカーは、活動基準原価計算(Activity-Based Costing = ABC)をあげています。
ABCは、活動に着目して原価計算の対象に適切にコストを負担させようとするものです。コストの大半を占める間接費を適切に配分することができます。主目的は、製品原価の合理的な算定を通じて製品戦略に活用することです。
ABCの発展形として、ABM(= Activity-Based Management:活動基準管理)があります。顧客が受け取る価値を改善し、原価を低減し、利益を改善します。主目的は、活動やプロセスの改善による原価低減であり、業務改革やリエンジニアリングに活用できます。
さらに、これらの発展形としてABB(= Activity-Based Budgeting:活動基準予算)があります。作業の負荷と資源の必要量の見積もりを支援するためにABCを活用し、予算を編成するものです。
(参考文献:櫻井通晴『ABCの基礎とケーススタディ』東洋経済新報社)
ドラッカーは、これらABC、ABM、ABBの全体をABCで総称していると考えられます。
ABCは、プロセス全体のコストを把握し、管理しようとするものであり、機械の遊休時間、材料や工具の待ち時間、出荷の待ち時間、不良品の手直し、廃棄処分のコストなど、何もしないことに伴うコストも計算します。
原価計算基準のように、恣意的になりやすい方法で間接費を配賦することがありませんので、コストと成果を正確に関連づけることが可能になります。その結果、そもそもその活動が必要かどうかを問題にすることができるようになり、もし必要だとしても、どこで行うべきかを問題にすることができるので、成果の管理を可能にします。
ABCは、活動に着目するので、製造業だけでなくサービス業でも活用できます。サービス業では、通常、直接原価を算定するという考えはなく、事業の全プロセスに関わるコストがすべて全体として管理されてきたため、ABCの活用による成果は製造業よりも大きくなります。
余計な活動がないとすると、顧客一人当たりのコストは固定と考え、顧客一人当たりの成果(サービスの量と組み合わせ)を大きくしようとするようになります。例えば、小売りの陳列棚は一定の固定費であるため、同じ陳列棚からの利益を最大にするような棚割りを考えるようになります。
サービス業に適用できるのであれば、研究開発など知的なサービス活動にも適用できるようになります。当然、多くのオフィスワークにも活用できます。
サプライチェーン・マネジメント
コストの情報に関しては、自社の情報だけではなく、経済活動の連鎖(サプライチェーン)全体のコストを把握し、管理し、成果を高めようとすることが重要になります。
顧客が支払うコストはサプライチェーン全体のコストであり、企業の境界は全く関係ないからです。
さらに、コストに利益を上乗せする価格設定ではなく、顧客が支払ってくれる価格を基に、サプライチェーン全体のコストを管理するようにしなければなりません。
そのためには、サプライチェーンに参加しているすべての企業が、統一的な、少なくとも接続可能な会計システムをもち、情報を共有しなければなりません。
富を創造するための情報
企業が収入を得るのは、コストの管理によってではなく、富の創造によってです。顧客は価値に対してお金を払いますから、価値の創造が富を創造します。そのために必要な情報が4つあるとドラッカーは言います。これらは現状についての情報であり、いわば戦術を教えるものです。
基礎情報
会社の現状についての基礎的な判断材料です。人間にとっての定期健康診断結果に当たります。
ドラッカーは、基礎情報として、キャッシュフローや資金繰りについての情報、販売数量や売上額、売掛金などの情報をあげています。
例えば、自動車ディーラーであれば、在庫台数と販売台数の比、社債の金利支払いと収益の比、売掛金(半年超と総額)と売上高の比などが重要です。
基礎情報は、正常であれば特別な対応を要しませんが、異常であれば、問題を発見し処置しなければなりません。
生産性情報
すべての生産要素について、生産性の情報が必要です。
ドラッカーは、EVA(= Economic Value Added:経済付加価値)が有効であると指摘しています。EVAは、資金のコストを含むあらゆる種類のコストを考慮したうえで、付加した価値を把握しますので、生産要素のすべてに対する生産性を測定することになります。
EVAは次のように定義されます。
EVA = (収益の比率 – 資本コスト) × 資本
「収益の比率」とは、資本に対する税引後営業利益の比率です。
「資本コスト」とは、資本に対する調達コストの比率です。調達コストとは、資本の拠出者が要求する利益であり、借入金の場合は「利息」、株式投資の場合は「配当」になります。
(参考書籍:G.ベネット・スチュワート.Ⅲ『EVA(経済付加価値)創造の経営』東洋経済新報社)
通常、会計上の「税引後利益」は税金を支払った後に残る利益ですから、税引後利益がプラスであれば、会社の手元に利益が残ったと考えます。しかし、株主への配当は税引後利益から支払われますので、配当を支払ってもなお利益が残らなければ、本当に利益を生み出したことにはなりません。
また、税引後利益が少なかったという理由で、株主が当初期待した配当が支払われなければ、必要な利益をあげられたとは言えません。
ですから、ドラッカーは、「EVAは実際に生産過程の全要素の生産性を測るもの」であると評価しています。EVAがマイナスであれば、たとえ会計上の税引後利益がプラスであっても、富を生み出したことにはならず、社会にとってマイナスを生み出す企業であるということになります。
ちなみに、「税引後利益」は利息が引かれた後の利益ですが、EVAの計算式では、利息は「資本コスト」の方に含まれます。ですから、「収益の比率」では、利息を足し戻した「税引後営業利益」が使われます。
もう一つあげているのは、ベンチマーキングです。自社の仕事ぶりを、最高の仕事ぶりを行っているリーダー企業と比較するものです。グローバルな競争力をもつために必要になります。
強み情報
市場や顧客の価値と、自社の特別の能力を結合するためのコア・コンピタンス(中核的競争力)の情報が必要であると言います。
コア・コンピタンスを発見するのは簡単ではありませんが、自社および競合の仕事ぶりを丁寧にフォローし、予期せぬ成功と予期せぬ失敗を見つけることが重要であると言います。
予期せぬ成功は、市場が高く評価し、喜んで支払いを行ってくれるものを明らかにします。リーダー的な地位を得るために必要な優位性の存在を教えます。
予期せぬ失敗は、市場の変化や自らの強みの後退を教えます。
コア・コンピタンスは、個々の企業に特有の能力ですが、ドラッカーは、あらゆる種類の組織がもたなければならない共通の中核的能力があると言います。すなわち、イノベーションの能力です。
イノベーションについても、自らの業績を記録し、評価するためのシステムが必要です。ドラッカーは、次のようなシステムを提案します。
- 一定期間の業界全体のイノベーションの実績を徹底的に調べる。
- それらのうち、「本当に成功したものはどれか」、「それらのうちわが社のものはいくつあるか」を問う。
- 「わが社の実績は、当初の目標に見合ったものだったか」、「市場の方向性に合致していたか」、「わが社の市場地位に見合っていたか」、「わが社の研究開発費に見合っていたか」を分析する。
- 「わが社が成功したイノベーションは、成長力や機会が最大の分野におけるものだったか」、「逸してしまった重要なイノベーションの機会は、どのくらいあったか」、「なぜそれらの機会を逸したか」、「気がつかなかったからか、気がついていながら手をつけなかったからか、本気で取り組まなかったからか」を検討する。
- 「わが社は、イノベーションの商品化にどのくらい成功したか」を問う。
これらの問いの多くは、客観的な測定ではなく主観的な評価を求めるものです。答えを出すというより、新たな正しい問題を提起するものであると言います。
(参考:「コア・コンピタンス」とは何か?)
資金と人材の情報
組織の行動に直接関わる資源の情報です。この2つの資源が、優れた業績をあげられるか、貧弱な業績しかあげられないかを決めると言います。
資金の情報に関して、最も重要なのは、一度に多額の資金を要する投資案を評価する場合です。投資案の評価指標には、次の4つがあります。
- 収益率
- 回収期間
- キャッシュフロー
- 現在価値
多くの企業では、これらのうちのいずれかで評価することが多いようですが、ドラッカーは4つの基準すべてを調べなければならないと言います。
さらに、機会とリスクの2つの観点から検討し、期待される成果の内容と期限も明らかにしておかなければならないと言います。要するに、これらすべてを一覧にした予算表が必要です。
また、ドラッカーは、特に次の2つの情報は重要でありながら、ほとんどの組織が手に入れようとしていないとも言います。
- 投資が約束した成果をもたらさなかったとき(投資案件の6割は、約束した成果をもたらさないと言います。)、何が起こるか。重大な損失が生じるか、それとも、さしたる損失は生じないか。
- 投資が成功し、あるいは約束した成果をもたらしたとき、何をしなければならないことになるか。
投資の成果は、必ずフィードバックしなければなりません。成果を記録し、当初の期待や約束と比較対照することによって分析しなければなりません。
人材の配置についても同様です。あらかじめ期待するものを明らかにしておき、配置する本人に明確に伝えておかなければなりません。そのうえで、成果を期待にフィードバックすることによって評価しなければなりません。さらに、配置のプロセス自体も評価しなければなりません。
それらはすべて記録しておく必要があります。人材の強みと弱みに関する重要な情報であり、今後の配置替にも活用できます。配置のプロセスに関しても、今後の改善に活用することができます。
組織の外部にある情報こそが重要
戦略に関わる情報は外部にあります。事業の成果は組織の外部で生まれ、変化は常に組織の外からやってくるものだからです。組織の外部にある情報とは、市場、顧客、非顧客、産業内外の技術、国際金融市場、グローバル経済などの情報です。
特に非顧客(本来、自社の顧客であってよいのに、現在、顧客になっていない人たち)が重要です。市場シェアがどれほど大きくても、非顧客の方が圧倒的に多いのが普通です。そして、非顧客の中で基本的な変化が始まり、重大な変化に発展していきます。自社の既存顧客だけに着目していると、その変化に気づくことができません。
さらに、この50年において、産業そのものを変えるような重要な技術の少なくとも半分は、その産業の外からやってきたものであると、ドラッカーは言います。したがって、常に外に幅広く目を向け、変化を見出し、自らの事業にとって機会として利用できないかを考える必要があります。
外の情報は、必ずしも容易に手に入るとは限りませんが、調べれば手に入る情報であっても、十分な注意を払わない企業は多いと言います。致命的な誤りの原因は思い込みです。自分たちの考えるようなものであるに違いない、自分たちが知っていること、自分たちが当たり前としていることと同じであるに違いないという思い込みです。
人は、思い込みを裏づけるような情報や、欲しいと思っている情報を集めてしまう傾向があります。その方向にアンテナを立てているからです。そのような現実を知ったうえで、正しい疑問を提起する情報システムが必要です。そのためには、そもそも自らが必要とする情報が何かを知り、それらを日常的に手に入れ、意思決定に反映させていかなければなりません。
情報の入手先
外部の情報源としては、データバンク、データサービス、専門誌、レポート、論文、調査結果などが活用できます。
ただし、外部の情報としてどのようなものが必要かを徹底的に検討するためには、外部の専門的な助けが必要です。企業の戦略に疑問を投げかけ、問題を提起する必要があるからです。
外部の情報サービス・コンサルタントなどを活用する方法があります。
自ら集める
外の世界の情報を都合よく手に入れる方法はなかなかありませんので、結局のところ、自分で外へ出かけていく方法が効果的です。
業績のよい企業は、経営幹部が定期的に現場で顧客対応をする習慣があると言います。実際にカウンターに立ったり、顧客を営業して回ったり、競合の店舗に足を運んで観察し、実際に顧客と話をしたりします。ボランティアに参加することは、まったく違う外の世界を知るうえで効果的です。
知識労働者に必要な情報
情報は組織として必要なだけでなく、知識労働者が個々の仕事を行ううえで必要なレベルの情報もあります。
知識労働者は外部から情報を取り入れ、自らの知識を適用し、情報をアウトプットして自らの成果とします。インプットは、組織の外からの情報である場合もあれば、同じ組織内の他の知識労働者のアウトプットの場合もあります。同様に、自らのアウトプットは、通常、他の知識労働者のインプットとなります。
情報が、組織内で知識労働者を結びつけています。情報によるネットワークが組織そのものでもあります。
ですから、各知識労働者は、次の点を明らかにし、知らせなければなりません。
- 共に働く人たちに、どのような情報を提供でき、あるいは提供すべきか。それはどのような形で、いつまでに提供でき、あるいは提供すべきか。
- 自分が必要とする情報は何か。それは誰から、どのような形で、いつまでに入手でき、あるいは入手すべきか。
これらの情報の内容は、会計担当者やIT担当者が分かるものではありません。彼らは、断片的な事実としてのデータを集約したり、データを処理・分析する道具を管理したりしていますが、各知識労働者の仕事に使える情報として整理していることは通常ありません。
データは、「何にどのように使うのか」という目的にしたがって、情報として体系化されます。
「何にどのように使うのか」は、知識労働者本人にしか分かりません。本人が、自らに期待される成果に基づいて、必要な情報を明らかにしなければなりません。
ですから、上記の2つの情報を相互に明らかにし、理解し、共有し合うことが、仕事のためのコミュニケーションとして不可欠です。
情報を得る目的は、仕事で成果をあげることですから、行動につながるものでなければなりません。問題が起こっているのであれば、それが大きくなる前に用意し、分析し、理解し、行動できなければなりません。どのような情報に意味があるかを十分に時間をかけて考えることが必要です。
成果が必要な情報を決める
仕事は、個人においても組織においても、常に成果からスタートします。期待される成果から、目標を定め、なすべき仕事を明らかにします。
期待される成果とは、顧客の中において生じる満足です。企業であれば文字どおり顧客ですが、個々の知識労働者であれば、その人のアウトプット情報を活用する人(通常は社内の別の知識労働者)です。成果が顧客の中で生じるのであれば、その成果が何かは、顧客に直接聞く必要があります。
ですから、知識労働者のコミュニケーションは、まず、上記の1.の情報について相手に聞くことから始めなければなりません。
ドラッカーは、情報の体系化には、基本となるいくつかのパターンがあると言います。これらのパターンを念頭においたうえでコミュニケーションを図り、必要な情報を体系化します。
優先順位による情報の体系化
中心的な課題によって、情報を体系化するものです。要するに、「何をするのか」、「何に使うのか」に従って体系化します。その都度、必要な情報を明らかにするためには、通常、この方法で体系化するのが一般的です。
課題は、情報を利用する本人が決めることになりますが、自らの仕事において期待される成果や目標に関わるはずですので、共に働く人たち、特に上司には知ってもらうべきことです。
蓋然性理論による情報の体系化
TQCの基本となっているもので、誤差内のことと例外とを峻別する考え方です。誤差内のことであれば行動する必要はないので、特に情報として体系化する必要はないものとします。
例外が起これば、情報として扱い、何らかの行動が必要であるものとします。
仕事がルーチン化でき、誤差内のことと例外とを峻別する基準をあらかじめ定めることができる場合は、この方法が利用できます。
敷居理論による情報の体系化
「一定の限界に達しない限り、意味のある変化と見る必要はない」とする考え方です。注目すべき指標があらかじめ明確にできるのであれば利用することができ、実際によく利用されています。
例えば、売上や利益の落ち込みが、一定期間、一定水準を超えたとき、意味ある情報ととらえ、不況と認定します。
一連の出来事が一つの傾向として定着したら、注目と行動の必要性が生じていることを知る必要があると考え、情報として扱うことにします。逆に、重大事に見えたとしても一時的な事象であれば、意味のある情報としては受け取らないということにもなります。
尋常ならざることの報告による情報の体系化
ドラッカーが提案した「マネジャーへの手紙」による情報の体系化です。
部下全員が、毎月一回、仕事の場での異常なことや予期せぬことを上司であるマネジャーに報告します。ほとんどは放っておいても問題ありませんが、例外的なことが、毎月毎月、一定の確率を超えて起こったり、いくつかの例外を組み合わせてみると重大である場合があります。
あらゆる仕事に利用できる方法です。報告基準があるわけではないので、主観的な内容な、取るに足らない内容も多く含まれると予想されます。
しかし、様々な考え方や見方をもつ複数の部下から報告させること、継続して報告させることによって、マネジャーが自らの中でデータを統合し、意味ある情報として体系化することになります。
人がAIに求めようとしているもの
現状において進行している情報革命においては、従来と同様に道具の革命も引き続き進行しています。
Iotによって、インプットされるデータはますます膨大になりつつあります。そのような膨大なデータを処理する過程でAIを活用し、価値ある情報を人間に代わって引き出そうとしています。
つまり、人間があらかじめ定めた基準やルールに従って、AIにデータを選別・分析させるというレベルを超えて、情報として取り出すための価値基準をもAIに探索させ、その結果を得ようとしています。これは、判断や意思決定まで委ねようとしていることと同じになります。
判断や意思決定を技術に委ねるということは、人間は技術の支配に下るということです。多くの人材、資金、時間を投入して、自らの支配者を生み出すつもりなのでしょうか。
技術は、人間の様々な活動を便利にし、時間と労力を節約する方向で発達してきましたが、その延長として、人間としての最後の砦まで節約しようとしているかのようです。
科学的探求心が原子核反応を発見・実用化し、原爆や水爆を生み出しました。それらを生み出した科学者たちは、それらが実際に人類にもたらした結果を目の当たりにして、衝撃を受けたようです。「まさかこんなことになるとは」と後悔した科学者もいたようです。
AIに関しても、同様のことが起こらないことを祈りたいと思います。大げさな作り話で済むなら、それに越したことはありませんが、安きに流れるのが人の性であることも事実です。
人は、完全な自由よりも、むしろ緩慢な従属を望む生き物のようです。自分で本当に欲しいものを探す手間をかけるより、売れ筋ランキングやAmazonのリコメンドに従ったり、SiriやAlexaのお勧めを受け入れる方が心地よいと感じる人も多いようです。
多くの人は、マスコミの報道を鵜呑みにし、マスコミが報道しないことは存在しないことと同じであるかのように振る舞います。マスコミは、自らが世論の代表である振りをしながら世論を誘導し、世の中の人たちは、マスコミが世論だから正しいのだと考えます。
多くの人は、自由よりも支配される方を自ら選んでいるように見えます。
AIの背後に、意図的な操作が加わったときの恐ろしさは計り知れません。私たちは、それをどのようにして知ることができるのでしょうか。