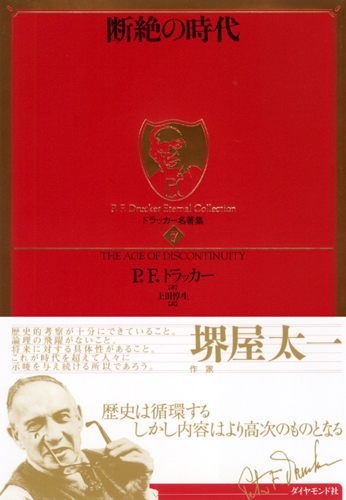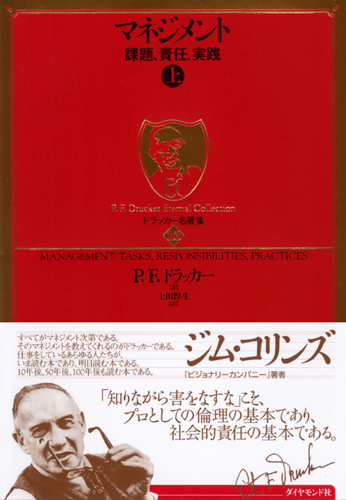これまでの経済発展のなかで、さまざまな経済理論が提唱されてきました。ニューエコノミクスが先進国で喧伝されたときも、その中身はさまざまでした。先進各国でとられた経済政策の背景となる経済理論もまちまちでした。
このような状況に対して、ドラッカーは、「健康な子どもがどんな医者にかかっても育っていくように、健康な経済は、どんな経済学でも発展していくというだけのことである。」と皮肉っています。
「経済の健全さは、政府エコノミストの数と力に反比例する」とさえ言われているそうです。
ノーベル経済学賞を受賞したスティグラーは、アメリカ政府による経済の統制、方向づけ、規制のうち、成功したものは一つもないことを明らかにしました。
グローバル経済の進展に対応して、経済学にも新たな理論が求められます。企業家精神とイノベーション、ミクロ経済、マクロ経済、グローバル企業の経済、グローバル経済を統合する理論です。それはおそらく科学的理論というより経済法則と言えるもので、個々の経済事象に関する理論的説明と、個々の問題に対する対応策です。
アメリカの経験
企業の動向
1980年代にアメリカの製造業はほとんど崩壊したと言われましたが、それは間違いです。
1980年代を通じて、アメリカの製造業は、世界市場におけるシェア(アメリカ・ブランド製品にして約20%)を維持し続けました。その間、世界の製品売上高は50%あるいはそれ以上伸びているため、アメリカ製造業の売上高は大きく拡大したことになります。
日本におけるアメリカ・ブランド製品の多くは、当初日本側が株式の過半をもつ日米合弁企業で生産されていましたが、ドル高を利用してアメリカ側が株式を買い取っていったため、アメリカ資本に移っていきました。
1980年代のアメリカの貿易赤字は、世界的な市況産品の価格と輸出の崩壊によるものです。アメリカは、歴史的に農産品と工業原料の世界最大の輸出国でしたが、そのいずれも国際市場価格が下落し続けました。特に、農業技術の進歩によって、多くの国は食料自給率を上げ、食料輸入大国がなくなっていきました。
アメリカの工業製品の主要顧客の一つである中南米諸国は原料生産国であるため、国際市場価格の下落の影響を受け、輸入購買力が減少しました。
さらに、アメリカの貿易赤字の原因の一つには、原油輸入の急増もありました。
ドル高は、アメリカ製造業の競争力を落としたわけではありません。
1985年には、急激な円高ドル安が始まり、15ヶ月後には半減しました。それにもかかわらず、原料価格は下落したドルに対してもさらに低下したため、アメリカでは、物価も賃金も上がらずに済みました。
だからといってアメリカの工業原料や農産品の輸出は増加しませんでした。他の国も同様です。
通説では、自国通貨の為替レートが下落すると、自国製品の国際価格が相対的に下がるため、輸出が増加します。一方、海外製品の国際価格が相対的に上がるため、輸入が減少します。ところが、アメリカではまったく逆のことが起こりました。
確かに、アメリカの輸出は大幅に増加したのですが、ドル安の1年半後であり、通説とは違いました。しかも、輸入の方は一貫して増加していました。
さらに別の通説では、自国通貨の為替レートが下落すると、その国の国債を保有している外国では、国債価値が減少するため、国債購入(投資)を減らそうとします。ところが、アメリカに対しては逆に、さらに投資が拡大し、アメリカの財政赤字を支えました。
だだし、当初は金融資産であったものが、実物資産に変わっていきました。ドル安で割安となったアメリカの企業や不動産が買われるようになったのです。これ自体は通常起こり得ることでしたが、アメリカのマスコミでは、特に日本が批判的に取り上げられることになりました。
ところが、さらに通説では起こりえないこととして、アメリカの企業は、ドル安で割高になっているにもかかわらず、外国企業の対米投資を超える対外投資を行っていました。アメリカ企業は、市場におけるシェア最大化を目指して、目先の利益を犠牲にしたのです。
為替と政策
アメリカの失業率が高いとき、カーター大統領(在任:1977年~1981年)はドルを250円から180円に切り下げました。輸出を伸ばして雇用を増やすためでしたが、失業率は下がるどころか、さらに上昇しました。
失業率が上昇すると、理論的にはデフレになるはずでしたが(フィリップス曲線)、実際はインフレが始まりました。
レーガン大統領(在任:1981年~1989年)は、インフレを抑えるために金利を上げました。実際にそのとおりになりましたが、その結果、高金利を目当てにドル買いが増え、ドル高になり、輸出(特に農産物)が打撃を受けました。代わりに輸入、特に日本からの工業製品の輸入が増加しました。
理論的には、輸出が減少して輸入が増えれば失業率が増加するはずでしたが、失業率は最低水準まで減少し、むしろ労働力不足に悩まされるようになりました。
そこで、レーガン大統領は口先介入でドル高を是正しようとしたところ、一度下がり始めたドルは野放図に下がり始め、250円から125円にまで下落しました。当然、大規模なドル離れが起こるはずでしたが、米国債の保有国、特に日本は、さらに米債権を増加させました。
同時に、ドルが大幅に下落したにもかかわらず、ドル建てでの一次産品価格が下落しました。
ドル安になれば、アメリカが輸入する製品のドル建て価格は上昇するはずでしたが、アメリカに輸出していた日本は、ドル建て価格を据え置きました。つまり、円建て価格を半値まで下げたことになります。
日本では、対米輸出による収益源を補うため、国内価格を引き上げました。理論的には、消費が減って貯蓄が増え(ライフサイクル貯蓄理論)、景気後退が起こるはずでしたが、逆に史上最大の消費ブームが起こりました。
教訓
原料経済と工業経済の分離
以上から得られる教訓は、原料経済と工業経済が分離され、原料経済が最重要ではなくなったということです。
これは景気循環理論に反しています。食料価格と原料価格の深刻かつ長期にわたる低迷は、その18ヶ月後に工業経済の深刻かつ長期の危機を招くとされていたからです。
証明済みの法則によれば、原料価格は、為替レートの変動に直ちに反応するはずでした。本来であれば、ドル安は原料のドル価格を上昇させるはずでしたが、ドル下落とともに、原料のドル価格がさらに下落し続けました。
原因としてドラッカーが指摘するのは、農産品について、世界的に生産過剰になったことと農業人口の減少です。農民の所得と購買力が、国民所得や国内購買力、消費者支出にほとんど影響を与えなくなったわけです。ですから、農民の所得は減少しているにもかかわらず、工業品の購買力に影響を与えていないのです。
ドラッカーは、原材料については、工業製品の総コストに占める原材料コストの比率が大幅に減少していることをあげています。原材料の価格が低下する以前に、原材料の消費量自体が大幅に減っているのです。
製造業が労働とも分離されてきていることも指摘しています。製造業における生産量は増加しているにもかかわらず、雇用量(総労働時間)は減少しているからです。
投資の重視
かつての海外進出では、貿易が先行し、徐々に投資が増えていくという状態でした。つまり、競争力の源泉である自国の生産要素を活用して生産したものを輸出する方法が優先でした。
今では、土地・労働・資本という伝統的な生産要素が競争力を左右しなくなり、世界経済における経済の主役は投資になりました。
市場を知っていること、市場への近さや感触を得ることが、もっとも重要なが競争力の源泉になったため、市場の内部で企業活動をし、シェアを確保することが重要になったのです。
グローバル企業化
企業が多国籍企業からグローバル企業に変わったことです。
多国籍企業は、出身国にある親会社と海外子会社群によって構成されていました。親会社が国内市場向けに製品の設計、生産を行っていました。子会社は、親会社が設計した製品を所在する国で生産し、販売していました。
グローバル企業では、親会社と子会社の区分は意味がありません。研究開発、設計、製造は、人材などを考慮し、経済原則に従ってグローバルに最適化されています。会社全体の資金は、国ごとではなく集中管理運用されています。トップマネジメント、戦略、事業計画、意思決定は、すべてグローバル化しています。
グローバル企業は、大企業であるとは限りません。中堅企業や小企業でも存在するようになっています。大きくない企業の方が政治的に目立たないため、自由度が高いとさえ言えます。特定の業種にも限定されていません。
そうなると、たとえ国内の限定された市場だけを相手に事業を行っている企業であったとしても、グローバル企業として経営しなければならなくなってきます。海外市場を対象にしていなくても、競争相手が、いつ、どこから進出してくるかまったく分からないからです。いつ、どこから進出してきてもおかしくないわけです。
シンボル経済としてのグローバル経済
グローバル経済は、資本の移動によって動かされ、形づくられます。しかも、資本自体は独自の論理で動いており、伝統的な経済合理性とは無縁です。
通説では、為替レートは実体経済を反映して変動すると考えられていました。そうであれば、変動相場制に移行した後のドル相場は、アメリカの貿易収支の動向に応じて変動するはずでした。
アメリカの貿易赤字が増加(輸入が増加)すれば、アメリカから輸出国に対するドル支払い(ドルの発行)が増え、輸出国は自国通貨と交換するためにドル売りを増やしますので、ドル安に動くはずです。ところが、ドルは非現実的な高さに維持されました。
ところが、一度ドル安に傾き始めると、とめどなく下落していきました。
要するに、資本の移動と実物経済は無関係になってしまったのです。資本はそれ自体で独自に動くシンボル経済になり、グローバル経済を支配するようになりました。世界での通貨取引量は、財・サービスの取引に必要な量の10〜15倍にのぼると言います。全体の90%以上は、実体経済とは別の論理で動いているということです。
ドラッカーによると、その別の論理とは、公定歩合や為替レートに関する政府決定、税制、財政赤字、国債発行等に関する見通し、政治危機に関する予測など、きわめて政治的な論理です。
為替レートの変動への対応
このような状態になると、企業は、為替レートの変動を不確実性のきわめて高い重大なリスク要因として対処しなければならなくなります。実体経済に応じた予測ができないからです。
国内の限定された市場のみを対象としている企業も無縁ではありません。競争相手がいつでも海外から参入し、為替レートの優位性を利用してくる可能性があるからです。
あらゆる企業が、為替リスクへの対応を日常コストとして認識せざるを得なくなります。
前提の陳腐化
経済学の問題の一つは、前提が陳腐化していることです。
均衡
まず、「均衡」を目標としている点です。例えば、完全雇用も一定の経済均衡によって成り立つと考えます。経済学では、経済発展は均衡を撹乱する要因であり、体系外として扱います。
しかし、ドラッカーによると、安定した均衡は不可能であり、経済発展による動的な不均衡こそが完全雇用をもたらすと言います。要するに、固定された経済は衰退する経済であり、経済発展を通じてこそ経済の均衡は得られるということです。
経済発展の理論にアプローチしたのは、ジョセフ・シュムペーターです。経済発展の要因はイノベーションであり、その担い手が企業家です。既存資源の最適配分を考えるのではなく、イノベーションによって富を生み出す能力を基本的に変化させるための経済政策が必要です。
利益
「利益」の扱いにも問題があります。経済学は均衡を目標にするため、利益は端役にすぎません。
各人は自らの利益を最大化するために利己的に行動しますが、その結果、完全市場においては、利益が特定のところに偏らない「均衡」が実現します。ところが、実際は市場の参加者がみな同じ情報をもっているわけではないため、特定の参加者に利益が集中したりすると考えられています。
そうだとすると、情報の不足がなければ均衡は実現できると思われがちですが、本質的に情報が足りることはあり得ません。経済発展を前提とすれば、未来の不確実性(リスク)が不可避だからです。
未来のリスクを負うためのコストを現在の生産活動から確保することが必要であり、これこそ利益の本質的な意味になります。利益は内部留保されて所有者に分配されることが目的ではなく、未来のリスクにかけて投入されなければなりません。
技術変化
「技術」の問題もあります。経済発展にも関わりますが、経済学では、技術変化や技術進歩を扱うことができません。
技術変化は、経済資源の使い方や配分の仕方を変え、生産性を変えるため、経済的な結果を変えます。その意味で、技術変化は経済的事象そのものです。
技術変化も未来の不確実性をもっているため、理論的に正確な予測をすることは不可能です。しかし、すでに起こった技術変化が経済に与える影響をある程度知ることは可能です。定量的に知ることは困難でも、影響が重大か微小かを知ることはできそうです。
問題は、影響を正面から取り上げようとしていないことであり、未だ起こっていない未来を予測しようとしていることです。
知識
「知識」の問題もあります。経済価値は「知識」であり、知識が生産性を高める本質的な要素であるというのが、ドラッカーの考え方です。経済学においても、その考え方を基本にして再構築される必要があると言います。
経済学では、生産要素として、労働、土地、資金、マネジメントを論じるようになりましたが(「資金、マネジメント」の代わりに「資本」をあげる場合が多いようです。)、ドラッカーによれば、いずれも生産要素というよりコストであり、制約条件です。互いにある程度代替可能でもあります。
経済発展の鍵は生産性であり、生産性を向上させるものは「知識」です。知識が投資機会をつくり、知識が従来の生産要素を生産的なものにします。
ドラッカーは、知識を扱う経済理論として、次のようなことを明らかにする必要があると言います。
- 経済的な成果への知識の影響
- 知識への経済の影響
- 知識の生産性の測定
- 知識産業(特に教育)における知識の生産と配分に関わる生産性の測定
- 経済発展に必要な知識の明確化
- 知識に関わる経済政策の決定(社会的、精神的、審美的、倫理的な観点を考慮。費用対効果の分析)
グローバル経済、マクロ経済、ミクロ経済の関係
グローバル経済と国内経済の関係
現在の経済学は、一国の国内経済学を扱っています。国外の経済は、国内経済への制約条件、修正条件、環境条件として考慮しているにすぎません。
国内で資金が循環し、地方の企業が全国的な企業に成長することは、国内経済にとって望ましいニュースとして取り上げられることが多いでしょう。
ところが、国境を超えて国際的に資金が循環し始めると、資金が流出している国はその資金流出を問題視し、資金が流入している国は外資による乗っ取りを問題視する、ということがあります。国際的な資金の循環によってグローバル企業が出現すると、どちら側の国からもよく見られず、敵視されるということも起こります。
経済がグローバルに循環しているなかで、ある国が国内経済の収支改善のみを考えると、グローバル経済に害を与え、巡り巡って自国経済にも悪影響を及ぼすことがあります。
現代は、グローバル経済が各国経済の拠り所となっています。グローバル経済の動きに応じて、国内の経済政策を規定しなければならない時代です。今や、国内経済をグローバル経済の一部として理解しなければなりません。
貿易の変遷
グローバル企業の出現は、世界の貿易構造を変化させました。
これまでの貿易理論には、財は移動しても生産要素は移動しないという前提がありましたが、グローバル経済とグローバル企業の出現によって、資本は国際的に移動するようになりました。
特に、真の生産要素である知識は特異です。ほとんど無制限の流動性をもつだけでなく、移動しても減少しません。移動の過程で知識はますます増大し、豊かになります。知識の移動は、同じ知識水準の国同士の方が容易です。
グローバル経済を動かしているのは、世界中を移動するシンボル経済です。そのなかで活動するグローバル企業も事実上無国籍です。ですから、経済的な超大国というものは存在し得なくなりました。
特定のグローバル企業が支配者になることもできませんが、今日、あらゆる産業において、アメリカ、ドイツ、イギリス、日本などの企業が世界的規模におけるスーパーパワー構造を形成するようになっています。
あらゆる企業の経営管理者にとって、企業戦略を考えるうえで中心になるのは、このグローバルなスーパーパワー構造です。
補完的貿易
国際経済学における貿易理論は、比較優位に基づいて行われるとされます。アダム・スミスの時代であった18世紀の貿易は、技術水準や生産要素が異なる国同士で行われる補完的貿易が主流でした。
互いに得意で相手がつくれない製品をつくり、交換する貿易です。
技術水準が同等の国同士の貿易(競争的貿易)は限定的にしか行われないことになっていました。
競争的貿易
19世紀中頃になると、世界経済にアメリカとドイツが参加するようになり、競争的貿易が出現しました。同じ分野で競争しつつ、相互に貿易をするものです。
例えば、ある化学品で競争しつつ、別の化学品を互いに購入しました。1900年頃には、競争的貿易が支配的になったといいます。
敵対的貿易
日本をはじめとする非西洋国が参入してくると、敵対的貿易が生まれました。競争を超えて、競争相手の戦闘能力を破壊することによって戦争に勝利し、産業を支配しようとするものです。
ドラッカーによると、日本は、自分が何を始めたかを理解していなかったといいます。
日本は、戦後、技術において、マーケティングにおいて、きわめて遅れていることを自覚していたため、外国製品、特にアメリカ製品から自国市場を守ろうとしました。
また、すでに市場ができあがっており、自分たちが技術を手に入れることができ、若干の改善によって相当量の売上が期待できる産業に集中して輸出努力をしました。
特に、当時、労働集約的であった産業で、教育訓練によって低賃金労働者の生産性を向上させ、競争力を身につけました。
このようにして、まず国内で外国との競争を排除し、徐々に貿易相手国の産業を破壊することによって市場における支配権を獲得し、新規参入者が挑戦できないような優越性を確保していきました。
補完的貿易は協力関係であり、明らかな相互利益でした。競争的貿易は戦闘的でしたが、通常の市場競争と同様、個々の勝者や敗者が生まれることはあっても、市場が拡大し、消費者に確実な利益をもたらし、経済発展に貢献し、究極的には相互利益になります。
敵対的貿易は競争相手を市場から駆逐してしまおうとするため、相互利益がありません。自国の市場は相手国に対して閉鎖的であったため、攻撃を受けた国は仕返すことが事実上できませんでした。
経済ブロックの形成
このような対応に対する答えが、経済ブロックの形成でした。欧州共同体や北米自由貿易圏などは、日本が念頭にあったことは間違いありません。
複数の国が集まった経済ブロックは、一国では小さすぎる産業に対して、生産と販売のための広い地域と市場を与えます。ブロック内では互恵的な貿易関係(相互主義)をつくることができます。投資や知的所有権などに関しても同様です。
マクロ経済とミクロ経済の関係
現在の経済学
近代経済学(ケインズ経済学およびポストケインズ経済学)は、マクロ経済学において発展しました。マクロ経済学は、一国における政府、国民所得、分配、金融、通貨、物価などを対象とします。
特に、貨幣量が個人と企業のミクロ経済を支配すると考えます。
ケインズより前の経済学では、財・サービスの実物経済が支配していました。なかでも新古典派経済学では、個人と企業が主役でした。
さらに、現代の経済学では、国民経済だけが意味ある経済であり、国境を越える経済取引も、主権国家の管理と運営によって左右されると考えます。
個人や企業は自由意志のもとで独自に行動していますが、ケインズによれば、それは気体という全体のなかで動き回る分子のようなものです。全体としては一定の平均値に収束すると考えます。その平均値に影響を与えるものは、政府による金融財政政策であるとしています。
さらに、ケインズは、個人が自分の金をどのような早さで使うか(貨幣の回転速度)も、社会的な習慣によって決まり、長期にわたって不変であると考えました。
要するに、ミクロ経済には経済全体を動かす力はなく、ミクロ経済で何が起こっても、マクロ経済に影響することはないとう考え方に立っています。ミクロ経済とマクロ経済との関係についての経済学が存在しないということです。
個人や企業のミクロ経済が主役
ところが、すでに見てきたように、マクロ経済モデルが予測することと、実際に起こっていることは大きく乖離しています。気体全体を構成する分子は、単なる分子ではなく、生きた有機体であるということです。
ミクロ経済の主人公である個人や企業は、単に外部からの影響(政府による金融財政政策)にお決まりの反応をしているのではなく、経済的に何が合理的であるかを主体的に決定し、行動しているということです。
個人の貨幣の回転速度についても、シュムペーターによると、いかなる経済政策とも無関係であり、予想できない形で、突然に、しかも急激に変えることができると指摘しました。こちらの方が事実と合致しています。
ミクロ経済学で使われる経済人モデルでは、利潤の最大化をもって経済的に合理的な行動であるとしますが、どの期間で評価するかによって、行動はまったく異なります。それを決めているのも、個人や企業です。
ミクロ経済の意思決定を左右する企業家精神
個人や企業の意思決定に影響を与えるのは、技術、革新、変化などですが、現在の経済学にはこれらを位置づけることができません。変化のない経済、均衡経済を前提にしているため、技術や革新や変化は外生変数です。
過去には、技術や変化をモデルに組み込もうとする試みもなされましたが、うまくいっていません。マクロ経済の要素である貨幣政策や信用や金利と、企業家精神や発明やイノベーションとの間に相関関係がほとんどないからです。
経済の主役は、マクロ経済ではなく、企業家精神や発明やイノベーションのほうです。マクロ経済はミクロ経済に対する制約条件であって、マクロ経済の状態が同じであっても、ミクロ経済の主体の反応は変わることがあり、経済全体も変えることがあるということです。
新しい経済学の必要性
ドラッカーが求めるのは、市場をあるがままに理解することです。
市場とは、資源配分のメカニズムです。市場は自律的であり、それ自体が価値や力学、決定力をもっています。よって、マクロ経済政策が市場を管理することはできず、市場にとっては制約条件にしかすぎません。
ドラッカーは、新しい経済学に次のような内容を求めます。
- 均衡理論ではなく、経済的な事象としての技術変化を理解し、組み入れることができる理論であること
- グローバル経済を記述できるモデルをもち、グローバル経済とマクロ経済の関係を理解できること
- ミクロ経済の主体こそが経済価値を生み出す真実の主体であることを認め、ミクロ経済の行動を理論化すること
生態系としての経済
これまでの経済学は、経済を、いくつかの変数が全体を動かすモデルとしてとらえていました。
ドラッカーが必要であると指摘するモデルは、経済を一つの生態系、環境、形態としてとらえるものです。個人および企業のミクロ経済、政府のマクロ経済、さらにはグローバル経済、経済ブロックの4つの相互に影響し合う領域からなるものでなければならないといいます。
しかも、どれか一つが支配的で、他は従属的であるととらえるこれまでの考え方を変えなければなりません。4つの経済はいずれも部分従属変数です。どれか一つが完全に独立し、他の3つを支配することはないと考えます。
統合的な理論
必要なのは、ミクロ経済、マクロ経済、グローバル経済を統合する理論です。ミクロ経済では、企業家精神やイノベーションも含まれます。グローバル経済では、経済合理性の観念が大きく異なり、意思決定の対象となる期間も大きく変わります。
1870年代、フランスのワルラス(1834年~1910年)は、数学モデルを導入することによって、経済学を自然科学的な学問にしました。統計的に有意なものだけが意味をもち、決定要因となり得ると仮定しました。
しかし、現代数学においては、複雑性の理論が進歩しつつあります。複雑なシステムは、短期については予測不能であり、統計的に有意でない要素によって支配されます(バタフライ・エフェクト)。どのようなことも外生変数として除外することができません。
スティグラー(1911年~1991年。1982年ノーベル経済学賞受賞)は、アメリカ政府による経済の統制、方向づけ、規制のうち、成功したものは一つとしてないことを明らかにしました。
先進国経済のような複雑なシステムにおいては、統計的に有意でない事象、取るに足りない事象が、少なくとも短期的には決定的な要因となり得ます。それを予測することも、管理することも不可能です。
おそらく、個人と企業のミクロ経済、国のレベルのマクロ経済、グローバル企業の経済、グローバル経済のすべての経済活動を予測し、コントロールすることのできる一つの新しい総合的原理を、科学的理論として手に入れることは困難です。
現状において経済学が与えることができるものは、個々の経済事象に関する理論的説明と、個々の問題に対する対応策だけです。このような状態は、医学においても同様です。万病のための特効薬はなく、生命に関する包括的理論もありません。工学も同様です。
「天候」から「気候」へ
経済学は、短期的な変動に当たるような経済の「天候」をコントロールすることはできません。「天候」をコントロールするための経済政策は無効です。
政府がなすべきは、長期的な影響である経済の「気候」を正しく維持することです。体を整え、鍛え、健康を維持する方法を教え、病気の予防を説く医者のようなものです。
経済政策としては、経済的な構造、すなわち生産性、競争力、長期的マネジメント、産業構造、研究開発、官民の関係、労使の関係などを重視することです。これらが経済の実体や国の豊かさを決定する要因だからです。
ドラッカーは、近代経済学が消費者の利益のみを重視し、その他のあらゆる要因(雇用や生産など)は政治的であるとして軽視してきたことを問題視しています。日本、韓国、ドイツの経済政策は、自国の競争力強化のために、消費者を生産者の下に位置づけ、現に成功してきたといいます。
消費者の短期的利益を極大化することによって、富を生み出すための長期的な能力を自動的に手に入れることはできません。必要なことは、消費者に対する短期的な関心と、生産性や競争力に対する長期的な関心とを均衡させることです。