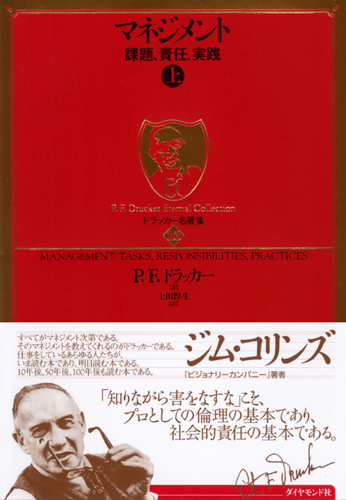リチャード・ルメルト(Richard P. Rumelt)は、戦略論と経営理論の世界的権威で、ストラテジストの中のストラテジストと評されています。
この記事では、『良い戦略、悪い戦略』(GOOD STRATEGY, BAD STRATEGY)および『戦略の要諦』(The Crux: How Leaders Become Strategists)を基に、ルメルトの戦略論を概説します。
成長ペースが鈍化したこと、成長が遅いことを問題であると考え、「わが社の重要課題は成長だ」と言う経営者は少なくありません。
製品や市場が成熟してくれば、成長ペースが鈍るのは当然です。問題は、成長しないことや成長しなくなったこと自体ではなく、その原因です。
根本原因が分かれば、それを解決するためになすべき課題を明らかにし、具体的な行動に落とし込みます。それが戦略です。
成長が課題だという企業の診断は、その企業の過去の実績と予想から始めます。成長期待と企業規模とのバランスを検討することが必要です。
全事業の成長を目指すのは現実的ではありません。戦略においては、新しい事業やラインの妥当な成長を目指します。
成長が課題だという場合、本当の課題は、競争圧力、組織のアジリティ(俊敏性)、起業家精神です。最重要ポイントを見極めるためには、この3つの要素を正しく評価することが必要です。
さらに、どのような価値を創造して成長を生み出すのか、そのしっかりした根拠と実現のためのメカニズムを持っていなければなりません。
なお、メディアが急成長中の企業をもてはやす状況に振り回されることなく、成長が価値創造による利益を伴うとは限らないことを忘れてはいけません。価値創造による利益を伴う成長はめったに実現できないし、実現できても気をつけないとあっという間に終わってしまいます。
成長の意味とメカニズム
成長とは、成功を示す指標が向上することです。企業の場合、特に売上高と利益について言うことが多いでしょう。
経営者の中には、自社あるいは業界には一貫した成長性があると主張する人がいますが、ルメルトの経験では、業種や企業よってはもちろん、同じ企業でも年によって実にバラバラであり、一貫性などどこにもないといいます。
経営者は自社の株価が上がることを望みますが、企業の成長と株価の関係は直接的でなく、単純でもありません。
株式市場は企業の将来の配当性向や合併買収などの予想を総合したうえで現在価値に割り引くので、ノイズの多いメカニズムです。
自社の株価が概ね市場平均に沿って推移しているとするならば、市場が自社に特に新しい価値創造を期待していないことを意味します。
急成長には魅力がありますが、必ずスローダウンし、マイナスに転じることもあります。株価がいち早く反映するのは、この急成長を巡る不確実性です。成長企業の場合、市場は常に成長の終わりが近づいている可能性を織り込みます。
結局、経営者がどれほどうまく経営して業績を上げたかではなく、その経営者に対する当初の予想をどれほど上回るかで株価は決まります。
よって、成長企業の経営陣の仕事は、自社にまだまだ成長余地があると示して市場を驚かせることです。低成長企業の経営陣の仕事は、業績を上向きにして市場を驚かせることです。
ユニークバリューを提供する
成長する市場に、その企業ならではの特別な価値を提供することが、圧倒的に多くの場合に事業で成功するための基本方程式です。
既存企業の場合、価値創造によって株価を押し上げるための重要な要素は2つあります。戦略的有効性と戦略的拡張です。
戦略的有効性とは、わが社にだけ生み出すことのできるユニークバリューを創出し、かつ、その生み出した価値を競争相手による侵食や模倣から守ることです。
価値を計測するには、バリューギャップ、すなわち買い手が払ってもよいと考える金額と売り手に発生したコストとの差に注目します。
ユニークバリューの価値は、競合他社とのバリューギャップの違いで計測できます。供給コストを引き下げても、買い手にとっての価値を高めても、ユニークバリューは増えます。
戦略的拡張とは、ユニークバリューをより多くの買い手または他の類似製品またはその両方に拡張することです。
不要な活動を排除する
事業は、消費したリソース以上のものを生まないのであれば不要です。消費したリソースは財務報告に表れることもあれば、表れないこともあります。
リソースには、資金もあれば、社会的な評判や経営陣の注意といった無形のものもあります。
成長プログラムの対象から外されるような事業は、もっと重要な事業から時間とエネルギーを奪っていることになります。
成長中の事業と安定した事業では、必要な管理、報酬、スピードや機敏さが違います。両者が混在していると、どちらの効率性も低下しかねません。人間が一度に取り組める課題の数には限りがあるからです。
企業が成長するためには、そうした不要な事業を刈り込み、成長が期待できる事業にフォーカスすることが必要です。経営陣の仕事も整理され、フォーカスするメリットを一段と活かせるようになります。
機敏であれ
競争の激しい状況では、反応時間が極めて重要な意味を持ちます。新しいチャンスや懸念すべき兆候に対して、真っ先に反応した企業が勝つことが多いのです。
空軍戦闘機兵器学校(FWS)の教官であったジョン・ボイドは、ボイド・ループと呼ばれる意思決定理論を編み出しました。
航空戦で勝つパイロットは「ループを素早く一周する」といいます。「ループ」とは、「観察(Observe)」、「状況判断(Orient)」、「意思決定(Decide)」、「行動(Act)」です。これらの頭文字を取って「OODAループ」とも呼ばれます。
企業経営で機敏さがとりわけ重要になるのは、顧客対応と新製品の開発・市場投入のサイクルです。
遅れをとったと感じたライバルは、その後の状況判断を誤りやすいので、レースで実際にリードするよりも、こちらがリードしているのだと敵に思わせるほうが重要であるとボイドは指摘します。
通常、規模の大きい複雑な組織は動きが鈍重です。例外は、組織の幹部が一貫性のある戦略を立て、協調し、信頼を勝ち得た場合に限られます。
合併・買収を活用する
M&Aを行った企業の時価総額だけに注目すると、その効果は芳しくないといいます。大型案件ほど惨憺たる失敗に終わっているからです。
M&A研究の大半は、買収発表の3日前から3日後までの非常に短い期間における株主利益に注目します。このアプローチは、すべての利用可能な情報が完全に市場価格に反映されているとする効率的市場仮説を前提にしています。
M&Aの効果は上潮のようにどっと押し寄せてくる傾向があり、効果測定の多くが上潮の間に行われているということです。
しかし、潮は必ずピークに達すると引き始めます。買収した側は自分の買い物を再点検し、大規模なリストラを実行に移します。
こうした再編プロセスは、M&A分析でイベントとみなされないことが多いため、M&Aのプラス効果だけが強調され、その後のマイナス効果はなかったことにされてしまいます。
だからといって、M&Aで付加価値を高めることは期待できないというわけではありません。M&Aで企業が成長を実現するためには、いくつかルールがあります。
M&Aは自社の基本的な競争戦略を加速または深化させるためのものであり、そのフォーカスを見失わないことです。M&A自体で売上高や利益を増やそうなどと考えてはいけません。
複雑な組織、事業範囲が広く製品が他分野に及ぶ多角的な企業、従業員数が非常に多い企業を買収してはいけません。そうした企業を統合するには何年もかかるからです。
対等合併には絶対に足を踏み入れてはいけません。誰が何の責任者になるかを巡る内部抗争で何年も浪費することになるからです。
意味のある成長の基本は、ユニークバリューの提供です。自社の価値を高めるような買収、新規市場の開拓を加速してくれるような買収には価値があります。ルメルトは、次の2つの企業の買収に限定すべきであると指摘します。
- 現行戦略を補ってくれ、かつ自前では開発できないようなスキルとテクノロジーを持つ企業
- 主要製品の市場アクセスを拡大強化してくれるような企業
買収した事業が親会社の本業にプラス効果を与え、スキルや市場での地位向上に寄与するよう統合していくのは容易ではありません。こうしたテコ入れ効果が得られないときは、ベンチャーキャピタルかPE(プライベート・エクイティ)ファンドを見習うとよいです。
大型案件の多くは、古くて成熟した巨大企業であり、人生の喜びを取り戻したがっているような老舗企業です。こうした企業に企業家精神があるとすれば、現場にいる若手だけでしょうから、もう若くはない経営幹部にとって唯一刺激的な仕事といえばM&Aです。
悪しき意図から無駄に大金を垂れ流すM&Aに手を出すCEOもいます。企業規模が大きくなることによってCEOのボーナスの決め手となる売上高などの指標が押し上がるからです。
巨大企業は、内部留保が潤沢であるためにM&Aに大金を投じたくなりますから、対価を払い過ぎる傾向があるようです。結果として、減損計上、人員削減が続くことになります。
合併・買収では必要以上に払わない
多くの研究が企業買収に否定的な結論に至った理由の一つは、買収する側が価値以上に払ってしまうことにあります。
上場企業を買収するときに特にそうなりやすく、経営権を握るために本来の価値の大体30〜40%の上乗せを払います。相手企業が上がり調子だと、プレミアムは一段と大きくなります。そこに競争相手が出現しようものなら尚更です。
この手の水増し取引を避けるためには、できるだけ非公開、非上場企業を買収することです。競り合いになる可能性も低いでしょう。
プレミアムが膨らむもう一つの原因として、自社株で払うケースがあげられます。自社株を発行するため、株価にも影響を及ぼします。上場企業による株式発行は概ね株価を2〜3%押し下げると言われ、大型案件の結果が統計的にみて芳しくないのは、ここに一因ががあると考えられます。
M&Aは、自社の本業と関連性の高い事業を買収するときに最大のシナジー効果が期待できると考えられていますが、必ずしもそうではありません。
買収における事業の関連性を調べた研究によると、株価動向に及ぼす総合的な影響はごく小さいといいます。シナジー効果への影響も、高い買収プレミアムを埋め合わせるほどではありません。
過大なプレミアムがつく最大の原因は、ルメルトによると、自信過剰です。シナジー効果の過大評価、過度に楽観的な成長期待、ターゲット企業の経営不振を解決できるという根拠のない確信などです。
行動経済学では、このような自信過剰を「準拠集団無視(reference-group neglect)」と呼びます。自分のスキルや過去の実績ばかり考え、他人のスキルや実績を考慮しない傾向が、これに該当します。
ターゲット企業の実際の価値以上に払わなければならない要因は、ほかにも存在します。相手が唯一無二の知的財産を持っていたり、市場で特別な地位を占めていたりして、この企業と競争したくない場合などです。
寡占化が進む業界で自社のプレゼンスを誇示するために、プレミアムを払って同業者を買収せざるを得ないこともあります。
バケモノを育てない
「バケモノ」とは、古い組織の中枢に巣食うシステムのことです。長年の間に出来上がった決まりや規範や前例と、それを神聖視する官僚的な人間とで構成されます。バケモノがのさばっている組織は、必ず利害の対立や政治的駆け引きの温床になります。
こうしたバケモノを抱えた組織では、雑草取りをして風通しをよくし、フォーカスすべきことにフォーカスすることです。
成長するビジネスを育てるためには、組織の官僚化は避けるべきです。また、成長ビジネスによって出現した新たな選択肢を、バケモノに邪魔されないようにすべきです。
企業における成長機会のことを、ルメルトは「苗床」と呼びます。苗床は丹精に世話をする必要があり、またバケモノに食われないよう用心しなければなりません。
苗床はせいぜい6〜8本にとどめ、経営陣が成長ぶりに注意を払う必要があります。
リスクの大きい苗床を育てる場合には、外野の意見は聞き流すか遮断し、課題や経営方針に関して毎月意見交換を行うといった配慮が必要です。
苗床の育成は往々にして失敗しますが、だからといって担当マネジャーを罰したり解雇したりすべきではありません。そのような仕打ちは、庭の花にまで除草剤を振りかけるようなものです。
細工はしない
ウォール街のアナリストは、単に利益を増やすのではなく、予測可能な形で利益を増やしてくれる企業を好みます。
ところが、経済もテクノロジーも競争も予測可能ではありません。そこで、予測可能な利益を生むために、企業は利益の平準化を試みます。通常は発生主義をとる会計手法をいくらか操作して、利益の変動を均すわけです。
ある調査によると、経営幹部の97%が利益の平準化を好むといいます。ところが、ある研究によると、利益平準化を行う企業は、その後に株価の急落に見舞われる確率が大幅に高まるといいます。
別の研究によると、利益平準化と平均株価収益率の間には、過去30年間にわたり何ら相関関係は認められなかったといいます。