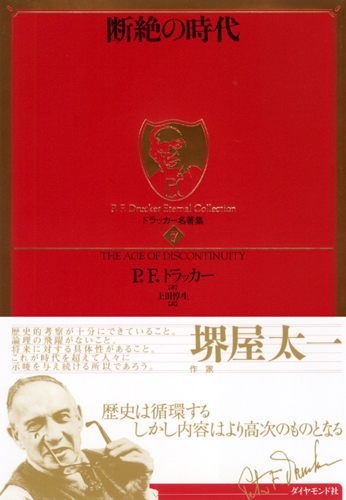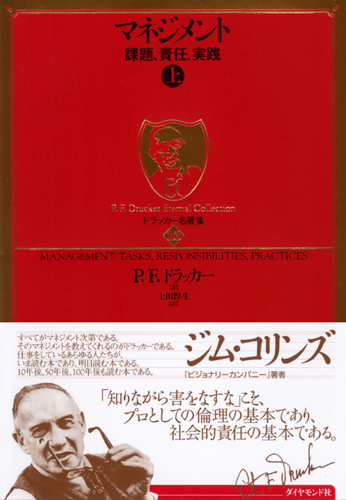組織が置かれている社会環境は変化するため、組織も変革しなければなりません。
組織の変革とは、通常、組織文化の変革ととらえられていますが、文化は様々な下位文化の複合でもありますので、一つの文化を変革するだけで組織全体の変革につながることはないと言われています。
組織文化の変革を総合的に行うのが組織開発であり、様々な手法があるようですが、現実には、組織文化の変更は非常に難しいと言われています。
一方、ドラッカーは、組織文化を変えてはならないと言います。変えるべきは組織文化ではなく、行動様式です。行動様式を変えるには、組織文化に根ざして行わなければなりません。変革は、それが大きなものであるほど、不動の拠り所が必要です。
『現代の経営』に見る組織文化の考え方
『現代の経営』では「組織の文化」という言葉が使われています。原語では「The spirit of an organization」(組織の精神)です。「culture」ではなく「spirit」ですが、「文化」という訳語が当てられています。ここでは、訳語に従って「組織文化」と表現します。
メンバーが組織の成果に貢献するためには、次の2つが必要です。
- 何を行うべきかを決めること
- それを実際に行うこと
何を行うべきかを決めるのは自己目標管理であり、行うと決めたことを組織として実際に行わせるものが「組織文化」であると、ドラッカーは言いました。
つまり、「組織文化」とは、メンバーを動機づけ、彼らの献身と力を引き出すものです。メンバーが最善を尽くすように仕向ける組織文化が求められます。
優れた組織文化は、投入した労力の総和を超えるものを生み出します。メンバーの強みに焦点を合わせて最大限引き出し、弱みを意味のないものにすることができなければなりません。
組織文化は人の行動に働きかけるものですから、ドラッカーは、優れた文化を実現するために必要とされるものは「行動規範」であると言いました。
行動規範は、単なる言葉や意図ではなく、実践のための行動原理です。漠然として曖昧なものであってはならず、目に見える行動として実践につなげられるほど具体的であり、評価できるものでなければなりません。
真摯さを前提とし、強みを重視し、卓越性を発揮させる動機づけとなるものでなければなりません。ドラッカーは、正しい組織文化を確立するために、次の5つの行動規範を要求しています。
- 優れた仕事を求め、劣った仕事や平凡な仕事を認めないこと
- 仕事自体に働き甲斐があり、昇進のためのステップではないこと
- 昇進は合理的で公正であること
- 人事など個人に関わる重要な意思決定には、決定者の権限を明記した基準が存在し(恣意的に行われないことが保証され、誰もがその基準を知ることができること)、不服がある場合の上訴の手段も用意されていること
- 人事においては真摯さを絶対条件とし、それはすでに身につけているべきものであって、後から身につければよいものではないことを明確にすること
『マネジメント』に見る成果中心の精神
『現代の経営』で「組織の文化」(The spirit of an organization)と題された章は、『マネジメント』では「成果中心の精神」(The spirit of performance)という題に変わりました。
組織にとって必要な精神として、「成果」を中心に位置づけることが明確に打ち出されました。同じ「成果」と訳される原語に「result」がありますが、ここでは「performance」が使われています。
結果という意味に重点がある「result」ではなく「performance」ですから、結果を導く優れた仕事ぶりや行動に焦点を合わせたものと理解されます。実践につながる行動原理であるという基本的な考え方は、『現代の経営』から変わっていません。
具体的な内容を、次の4つに集約しています。
- 組織の焦点は成果に合わせること。個人も組織も成果の基準を高くもち、成果をあげることを習慣化すること。成果は打率であり、失敗は許容されるが、自己満足と低い基準は許容されないこと。
- 組織の焦点は、問題ではなく機会に合わせること。
- 人事に関わる意思決定は、組織の信条と価値観に沿って行うこと。それらの意思決定こそ真の管理手段となる。
- 人事に関わる決定は、真摯さこそ唯一絶対の条件であり、すでに身につけていなければならない資質であることを明らかにすること。そしてマネジメント自身が自らの真摯さを明らかにしていくこと。
あげられている項目は変更があるように見えますが、その後に続く具体的な内容としては、基本的に同様であると理解されます。
変革すべきは組織文化ではなく「行動様式」
変化の激しい時代にあって、その変化に適応するため、組織もまた変化し続けなければなりません。
組織の変革は、通常、組織文化の変革ととらえられています。組織文化を変えることは、組織の枠組みを変えることと同義です。文化とは様々な下位文化の複合ですので、一つの文化を変革するだけで組織全体の変革につながることはないと言われています。
組織文化の変革を総合的に行うことが組織変革であるととらえられているわけです。ところが、現実には、組織文化を変えることは難しく、うまく行かないことも多いと言われています。
人に例えて考えると分かります。人の性格を変えることは非常に難しく、また、弱みを鍛えて強みにすることも困難です。少なくとも仕事において大事なことは成果をあげることですから、性格を変えたり弱みを克服したりしようとするのではなく、性格に合わせて、強みを生かせる仕事や仕事の仕方を選ぶことに注力すべきです。
ドラッカーの考え方は明確で、終始一貫しています。
- 変革すべきは、企業文化(組織文化)ではなく行動様式である
- 企業文化は捨てるのではなく利用せよ
組織文化の変革は組織を破壊する
元々、「文化」という言葉は、かなり広い意味をもち、様々な解釈もあるようです。
辞書で調べると、ある社会の成員が共有している「行動様式」や物質的側面を含めた「生活様式」を指しており、言語,思想,信仰,慣習,タブー,掟,制度,道具,技術,芸術作品,儀礼,儀式などから構成されるといいます。
組織文化は、「組織内で共有された価値や信念、習慣となった行動が絡み合って醸し出されたシステム」などと定義されます。客観的に目に見えるものではなく、具体的な形をもたないことが一般的です。
組織のメンバーも内面に取り入れて無意識に準拠しているため、明確に定義し、取り出すことは困難です。ですから、含まれる内容の範囲も組織によって区々であると言わざるを得ません。
しかし、確かに組織文化と呼ぶべきものは存在しており、内部のメンバーがそれに基づいて判断し、行動していることは間違いありません。内部のメンバーにとっては、暗黙的であっても判断や行動の拠り所となっています。
だからこそ、ドラッカーは、組織文化を変えてはいけないと言います。変えるべきは行動様式であり、組織文化に根ざして変革を行わない限り、意味のある有効なものにはならないと言います。
人間に喩えると、性格を改造することによって仕事ができるようになろうとするのではなく、性格に合った仕事の仕方に変えることによって、成果をあげようとすることです。
一般的な意味では、「文化」の中に「行動様式」も含まれると考えられます。ただ、ドラッカーの言う「行動様式」は仕事に関わることですから、他の書籍での記述などを総合して考えると、「仕事の仕方」といった意味で理解するとよいと思います。
最終的には、メンバーと協力して組織全体の目標に貢献できればよいので、組織全体として成果に焦点を合わせ、強みを生かして仕事ができるような方法に変えることが大事であるということです。
そもそも、組織文化の中に何が含まれ、何が含まれないかは組織によって異なり、明確に取り出すことも困難ですから、組織文化を変えるという事実上困難な課題に無理やり取り組もうとするのではなく、「行動様式」に焦点を合わせて変革に取り組むというのが現実的な対応であると言えるでしょう。
ドラッカーは、1950年代に日本を訪れた際、「日本の文化を守るためには経済の近代化が必要である」と言ったそうです。その後の1968年に発刊された『断絶の時代』では、「日本の文化を守るために社会の近代化が必要である」と言っていると理解されます。
経済や社会の仕組み(文化ではなく)を国際的な主流に適合させていくことによって、日本の文化を守ることができるということです。経済や社会の仕組みが、ドラッカーの言う「行動様式」に相当すると考えられます。
例えば、特定のイスラム教国家が国際社会との不適合を起こしているとすれば、現代に適合しない法制度や行動様式が妨げになっていることがあり得ます。そのような不適合が国際社会の反感を買えば、イスラム教文化全体にとっての排除圧力になりかねません。
トルコやマレーシアのように、イスラム教文化をもちながら西欧社会と協調できる国家が存在することを考えれば、「行動様式」に相当する部分で調和することによって、イスラム教文化を守ることができると考えられます。
組織においても、文化を守り、生き残っていくために、行動様式を変化させていかなければならないと言うこともできるでしょう。
文化に根ざして行動様式を変革した例として、ドラッカーは、戦後の日本をあげています。日本は、意図して伝統的な日本の価値観と文化の上に西洋の行動様式を据えた結果、近代化に成功したと言います。「和魂洋才」(古くは「和魂漢才」)といった言葉がそれを表しています。
一方、文化を変えようとして失敗した例として、インドや中国をあげています。自らの文化を変えなければ改革はできないと考えた結果、不満、摩擦、混乱をもたらし、行動様式は何一つ変わらなかったと言います。
人が新たな知識や技能を身につける場合も同様です。他者から学ぶことはできますが、身につけ方自体はその人の性格や特質を無視することはできません。他者がその知識や技能において優れているからといって、身につけ方自体を他者の方法でやろうとしても、うまく行くことはありません。自分に合った方法で身につけるべきです。
求められる行動様式の変化
組織に変化を求めている状況にはどのようなものがあるでしょうか。
- 顧客の価値観の多様化と変化の速さ
- 情報技術の更なる進展(IoT、AIの進化など)
- 少子高齢化
- 人口減少による市場の縮小と人手不足
- 働き方改革
などがあるでしょう。これらは明確に切り分けられるものではなく、相互に影響し合っていると考えられます。
最初の「顧客の価値観の多様化と変化の速さ」は、製品ライフサイクルの短縮化による製品開発のスピード化、顧客関係性の重視、多頻度小口配送の増加なども要求しているでしょう。
これらが組織に要求するものは、行動様式の変化です。端的に言えば、マーケティングの更なる重視です。マーケティングとは、顧客の欲求を起点として、組織のすべての仕組みや活動をつくり、行うことです。
顧客に対するマーケティングだけでなく、従業員や従業員以外の共に働く人たちに対するマーケティングも含まれます。直接雇用だけでなく、派遣労働などの非正規雇用や業務委託など、働き方の多様化が予想されます。
これまでは経営者の都合による選択であったものが、人手不足によって、働く人たちの多様なニーズに対応しなければならなくなっています。
行動様式を変える方法
ドラッカーは、行動様式を変える方法として、次の4つをあげています。
- いかなる成果が必要かを明確にすること
- 成果とは、組織の単なる目標達成とは違います。組織活動そのものに関わる指標ではなく、組織活動によって顧客の中に生じるものです。
- 顧客はいかなる満足を求めているのかを明らかにします。
- あらゆる顧客のあらゆる満足をわが社の成果にするわけではありません。あくまで、わが社の組織文化、特に組織の価値観や信念に合致する顧客とその満足を成果のターゲットとして選ぶことが大切です。
- 変化した行動様式をすでに行っているところを調べること
- 自らの組織のなかで、すでにその行動様式を実現している部門や支店、店舗がないかを調べます。成果をあげている部門等を調べることで、逆に、自らの組織文化に相応しい行動様式を導き出すこともできます。
- 同業他社で成果をあげている組織からも学ぶことができます。
- ドラッカーによると、ほとんどの場合、望まれる成果を実現する方法は、全く新しい方法ではなく、行うべきこととして以前から知られている当たり前のことでありながら、ほとんど行われていなかったことであると言います。
- 特に、自らの組織ですでにうまくやっているところが、自らの組織文化を生かして成果をあげる行動様式を行っていることの証明になります。
- 小さな組織で、複数の店舗や支店がない場合は、顧客を分析する方法もあります。売上や利益の大半を占める顧客は少数です。それらの顧客を分析することで、自らの組織文化の強みを知り、強みを生かせる行動様式を知ることができます。
- 組織文化に根ざし、かつ成果をあげる行動を奨励すること
- 経営者自身が「望ましい成果をもたらすために何をなすべきか」を問い続けなければなりません。
- 従業員に対しても、経営者は「成果に集中するうえで妨げになるようなことを、私はしていないか」、「成果に集中するために、私は何をすべきか」と問い、その答えに基づいて行動しなければなりません。
- 行動様式の変化に合わせて、評価と報奨を変えること
- 組織において、人は、高く評価され、報奨される行動を取ることが知られています。